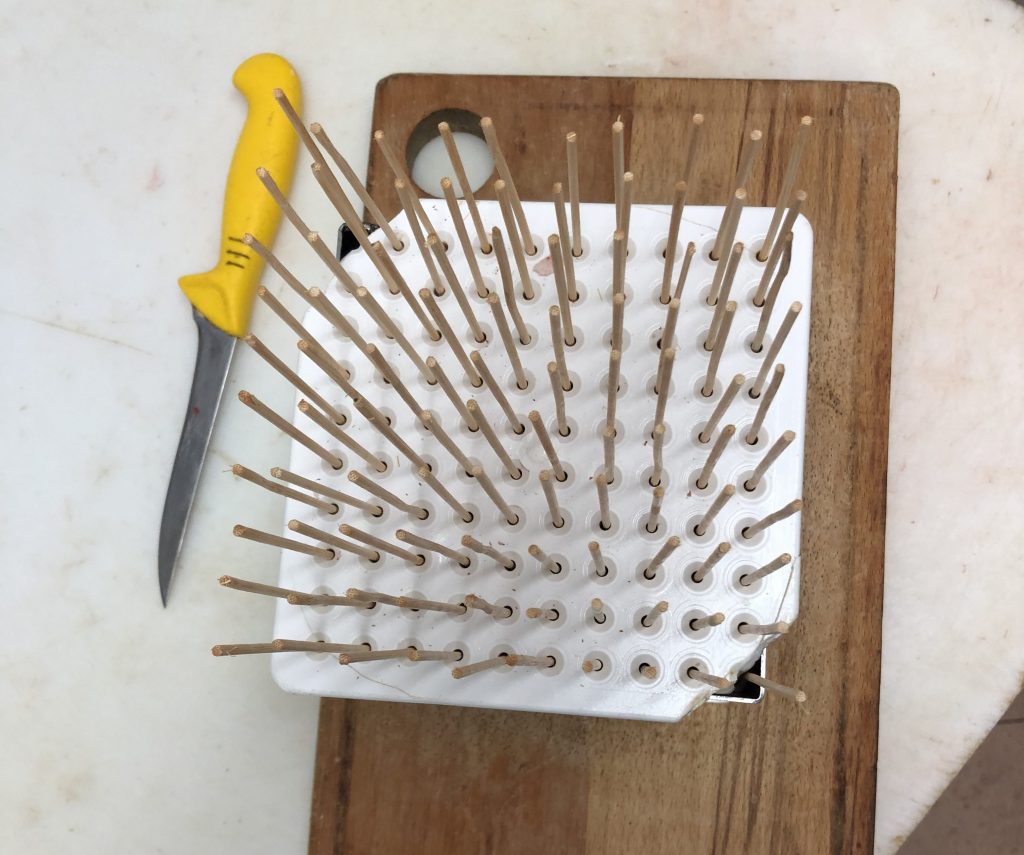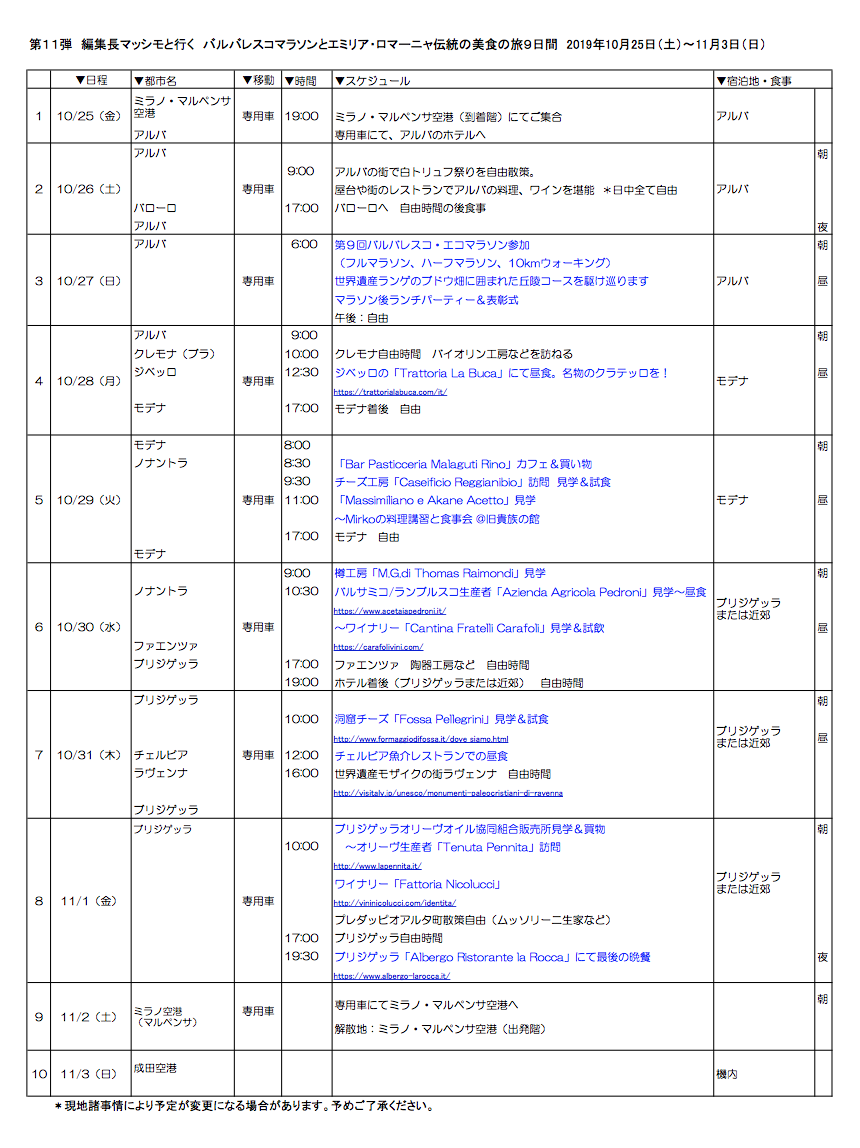Vol.37ヴェネト特集(2019/5/1発行号)より新たに応援団として『イタリア好き』を配布いただく事となった全国のイタリアズッキーニパートナーズ店舗をご紹介します!
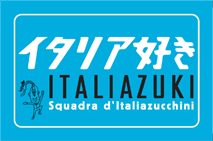 ★イタリアズッキーニクラブ・パートナーズ会員(定期読者会員)にお申込みいただいた際にお送りしている会員カードを持参いただくと、会員限定のサービスを受けられる店舗もございます。ぜひ店舗を訪れる際はカード持参で行ってくださいね。
★イタリアズッキーニクラブ・パートナーズ会員(定期読者会員)にお申込みいただいた際にお送りしている会員カードを持参いただくと、会員限定のサービスを受けられる店舗もございます。ぜひ店舗を訪れる際はカード持参で行ってくださいね。
(2019年7月19日現在)
【北海道】Semina(セミーナ)
住所:北海道札幌市中央区南一条西8-20-1 ライオンズMS 小六ビル 1F
tel:011-219-4649
WEB:http://trattoriasemina.com/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★パン+お通し無料
【山形県】ハレトケ
住所:山形県鶴岡市本町2-2-17
tel:0235-29-0071
WEB:https://www.facebook.com/本町バル-ハレトケ/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★コペルト(チャージ)無料
【埼玉県】おうじょう治療室
住所:埼玉県桜区田島4-9-12
tel:048-844-1314
WEB:https://www.oujou.net/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★初診料(2160円)を無料にいたします。
【東京都】Pizzeria Terzo Okei(ピッツェリア テルツォ オケイ)
住所:東京都港区新橋1-15-10 長井ビル1F
tel:03-6205-4057
WEB:https://www.bar-okei.com/
【東京都】Per caso(ペルカーソ)
住所:東京都千代田区神田神保町1-20 シャルール神保町1階
tel:03-6821-4911
WEB:https://www.percaso.jp/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★エスプレッソ一杯無料(お食事ご利用のお客様に限り)
【東京都】Osteria Chitarra(オステリア キタッラ)
住所:東京都江戸川区一之江7-30-6
tel:03-5879-9912
WEB:https://www.facebook.com/Osteria-Chitarra-1067651299914486
【東京都】Tiscali(ティスカリ)
住所:東京都品川区西五反田5-11-10 Relief不動前1F
tel:03-6420-3715
WEB:https://www.facebook.com/Tiscali.pastorare/
【東京都】Peri Peri(ペーリ ペーリ)
住所:東京都品川区西五反田1-15-10(五反田東急池上線高架下)
tel:03-6417-4994
WEB:http://www.facebook.com/periperi.arancino/
【東京都】Cuesta(ケスタ)
住所:東京都渋谷区道玄坂1-15-7 CENTRAL道玄坂1F
tel:03-6416-4224
WEB:https://www.facebook.com/202225880607110
【神奈川県】Solis(ソリス)
住所:神奈川県横須賀市湘南国際村1-2-8
tel:046-874-8750
WEB:http://www.solis-agriturismo.com
【神奈川県】Maresco(マレスコ)
住所:神奈川県逗子市逗子7-3-49 クリオンハウス1F-B
tel:046-827-7020
WEB:http://obiettivo.life
【愛知県】Osteria del Cuore(オステリア デル クオーレ)
住所:愛知県名古屋市天白区表山2丁目2404 NATURA八事ビル
tel:052-837-2882
WEB:https://cuore.nagoya/
【愛知県】医療法人鉄隻会 令和なかむらハートクリニック
住所:愛知県名古屋市中村区太閤6-32
tel:052-471-3832
WEB:http://www.tessekikai-clinic.com/
【兵庫県】イタリア語レッスン KOI(神戸~大阪)
住所:兵庫県神戸市東灘区森北町7丁目2-14
tel:080-7898-9383
WEB:https://www.kobeosakaita.com/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★レッスン料:500円引き
【福岡県】GELATO NATURALE(ジェラート ナトゥラーレ)
住所:福岡県福岡市東区水谷1-9-31
tel:092-231-9347
WEB:http://gelato-naturale.com
【鹿児島県】イルマーレ
住所:鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田815-92
tel:0997-43-5666
WEB:http://www.ilmare3.jp/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★グラスワイン1杯サービス
『イタリア好き』全国の配布店舗一覧
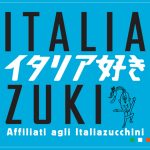 イタリア好きステッカーが貼られているお店が目印!
イタリア好きステッカーが貼られているお店が目印!
https://italiazuki.com/location/
▼イタリアでサービスが受けられるスポット↓
『イタリア好き』本誌をもって、イタリアを旅しよう♪
https://italiazuki.com/it/location/
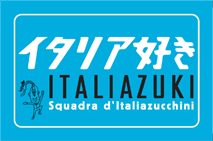 ★イタリアズッキーニクラブ・パートナーズ会員(定期読者会員)にお申込みいただいた際にお送りしている会員カードを持参いただくと、会員限定のサービスを受けられる店舗もございます。ぜひ店舗を訪れる際はカード持参で行ってくださいね。
★イタリアズッキーニクラブ・パートナーズ会員(定期読者会員)にお申込みいただいた際にお送りしている会員カードを持参いただくと、会員限定のサービスを受けられる店舗もございます。ぜひ店舗を訪れる際はカード持参で行ってくださいね。(2019年7月19日現在)
tel:011-219-4649
WEB:http://trattoriasemina.com/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★パン+お通し無料
tel:0235-29-0071
WEB:https://www.facebook.com/本町バル-ハレトケ/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★コペルト(チャージ)無料
tel:048-844-1314
WEB:https://www.oujou.net/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★初診料(2160円)を無料にいたします。
tel:03-6205-4057
WEB:https://www.bar-okei.com/
tel:03-6821-4911
WEB:https://www.percaso.jp/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★エスプレッソ一杯無料(お食事ご利用のお客様に限り)
tel:03-5879-9912
WEB:https://www.facebook.com/Osteria-Chitarra-1067651299914486
tel:03-6420-3715
WEB:https://www.facebook.com/Tiscali.pastorare/
tel:03-6417-4994
WEB:http://www.facebook.com/periperi.arancino/
tel:03-6416-4224
WEB:https://www.facebook.com/202225880607110
tel:046-874-8750
WEB:http://www.solis-agriturismo.com
tel:046-827-7020
WEB:http://obiettivo.life
tel:052-837-2882
WEB:https://cuore.nagoya/
tel:052-471-3832
WEB:http://www.tessekikai-clinic.com/
tel:080-7898-9383
WEB:https://www.kobeosakaita.com/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★レッスン料:500円引き
tel:092-231-9347
WEB:http://gelato-naturale.com
tel:0997-43-5666
WEB:http://www.ilmare3.jp/
《 会員カード持参で利用できるサービス 》
★グラスワイン1杯サービス
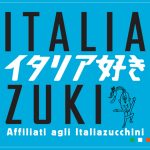 イタリア好きステッカーが貼られているお店が目印!
イタリア好きステッカーが貼られているお店が目印!https://italiazuki.com/location/
▼イタリアでサービスが受けられるスポット↓
『イタリア好き』本誌をもって、イタリアを旅しよう♪
https://italiazuki.com/it/location/