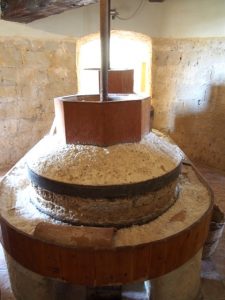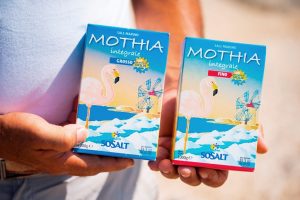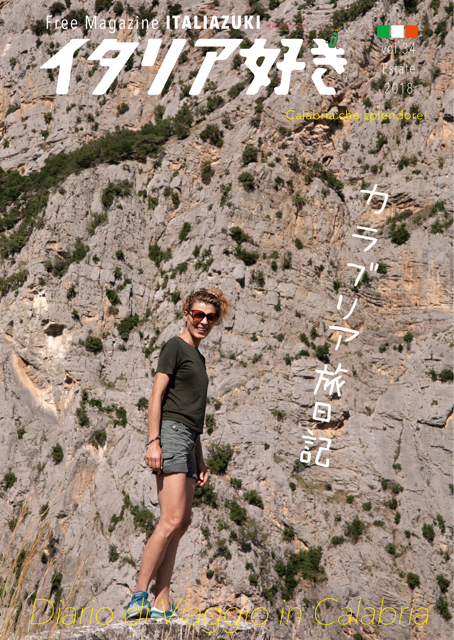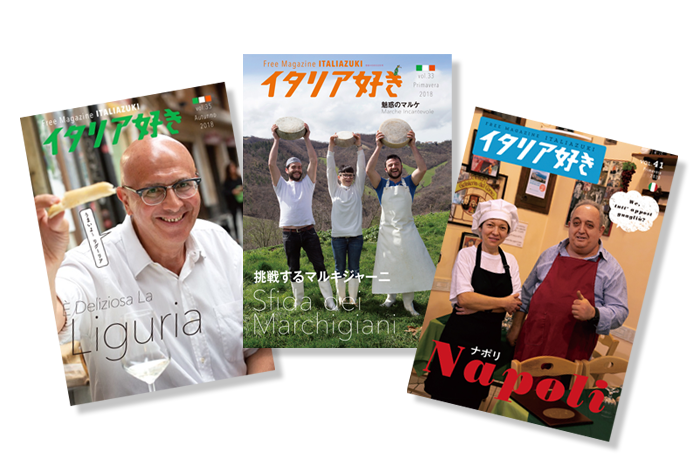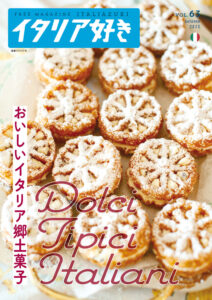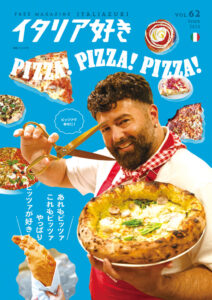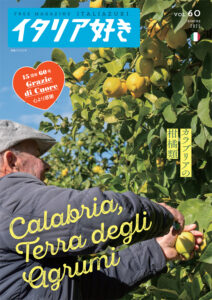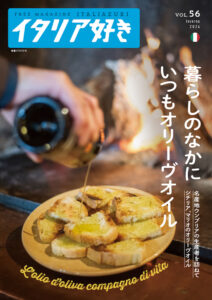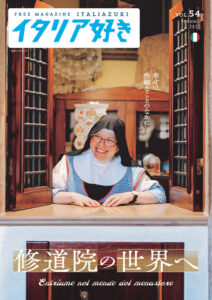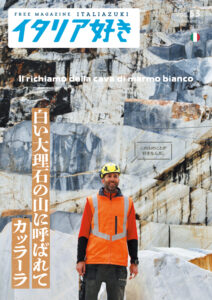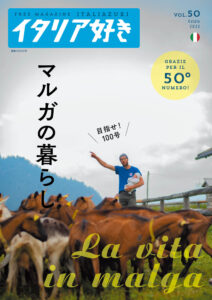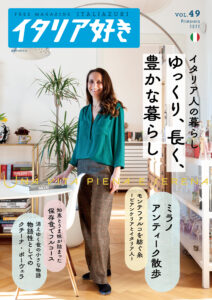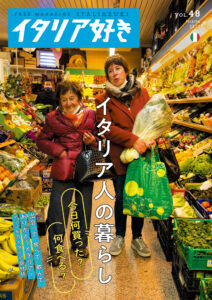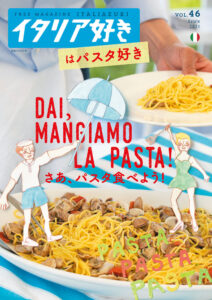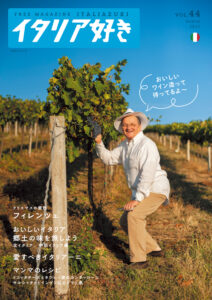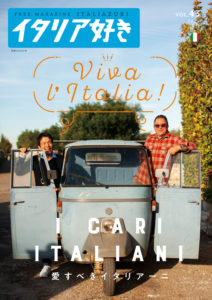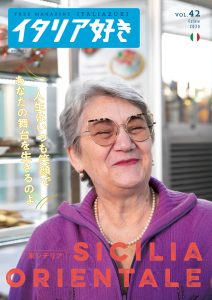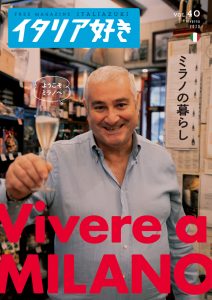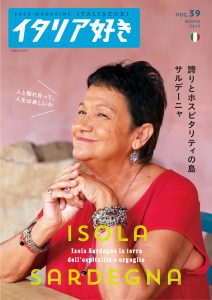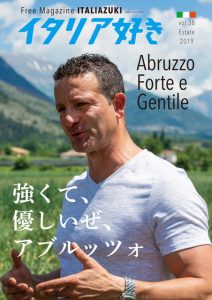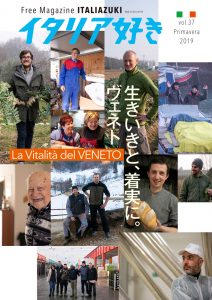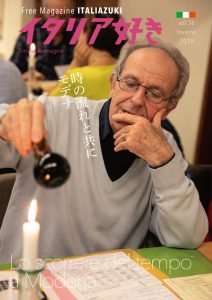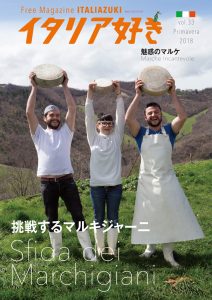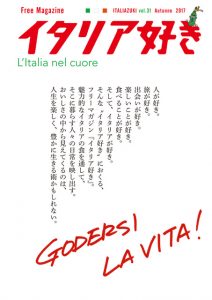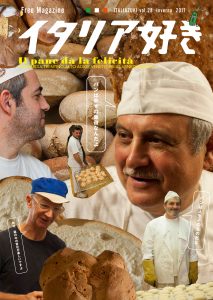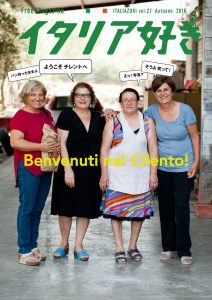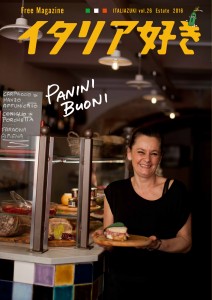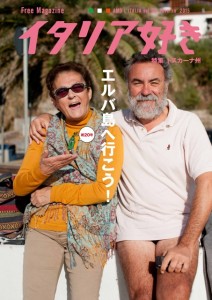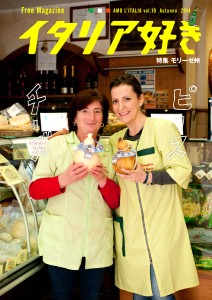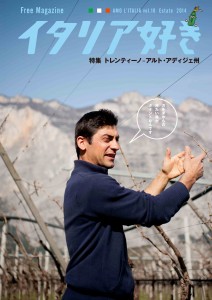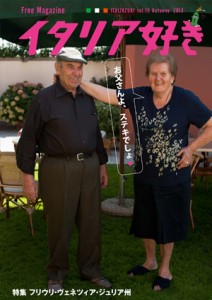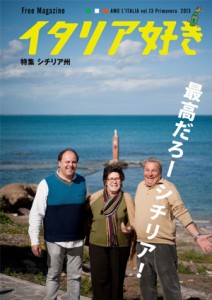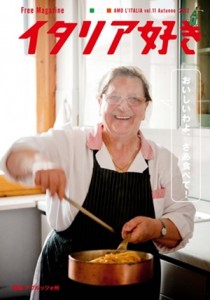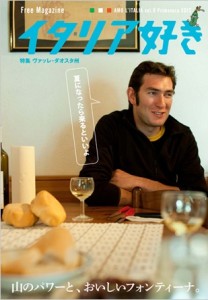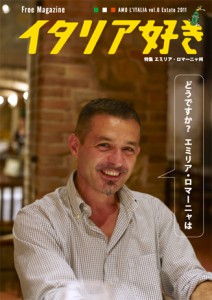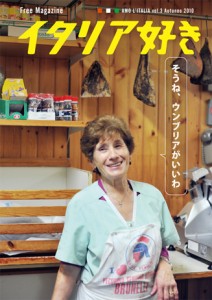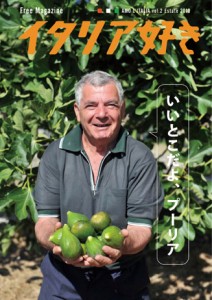vol.34カラブリア特集の発行に伴なって、渋谷のpinosalice(ピノサリーチェ)で開催したカラブリア食事会の報告。
いつもはシチリア料理をメインとしているpinosaliceで開くことになった理由はこちらへ↓
https://italiazuki.com/?p=28997
参加者の皆さん
《当日のメニューはこちら》
Piatto dalla Calabria
Pane del pellegrino,carciofo selvatico e bruschetta con n’duja / patate e pipi
突き出し カラブリア好き
巡礼者のパーネと野生のカルチョーフィ、ンドゥイヤのブルスケッタ、ジャガイモとパプリカのソテー
巡礼者のパーネ、ンドゥイヤ、野生のカルチョーフィは、取材先から持ち帰った現地の味。
野生のカルチョーフィは、鋭い棘の皮を剥くのが大変な作業。地元でもそれをやる人が減っている。
Antipasti 1
Carpaccio di pesce marinato al pomodoro e bergamotto
白身魚のカルパッチョ トマトとベルガモット風味
すみません写真ないですが、ベルガモット風味がカラブリア風。ベルガモットはレッジョ・ディ・カラブリアの特産品。
Antipasti 2
Crocchette di melanzane,melanzane marinato alla menta
ナスのコロッケと、ナスのミントマリネ
ナスの季節はナス料理責め。色々なレシピがある。
Primo
Fileja con peperoni e cruschi alla rosamarina
パプリカ、クルスキ、ローザマリーナの自家製フィレイヤ
カラブリアらしいパスタ! 生シラスの唐辛子漬けローザマリーナ。発酵具合がいい。
Second
Polpetta ripieni di n’duja al forno arrotolati con foglie di fico
イチジクの葉で包んだポルペッテのオーブン焼き ンドゥイヤ風味
イチジクの甘い風味と、ピリ辛のンドゥイヤのハーモニー。カラブリアにはイチジクの名産地がある。
Dolce
Tartufo di Pizzo
ピッツォのタルトゥーフォ
トリュフではありません。ピッツォ・カラブロという町の名物、タルトゥーフォの形をしたジェラート。地元では大人も夢中。
柳さんのカラブリア愛の溢れる料理に満腹、満足でした!
カラブリアに行かずとも、カラブリア気分満タン。
でも、行ったらもっといいんです。
柳さん、赤松さん、福田さん、そして参加者の皆さんありがとうございました。
いつもはシチリア料理をメインとしているpinosaliceで開くことになった理由はこちらへ↓
https://italiazuki.com/?p=28997
 |
 |
《当日のメニューはこちら》
Piatto dalla Calabria
Pane del pellegrino,carciofo selvatico e bruschetta con n’duja / patate e pipi
突き出し カラブリア好き
巡礼者のパーネと野生のカルチョーフィ、ンドゥイヤのブルスケッタ、ジャガイモとパプリカのソテー
巡礼者のパーネ、ンドゥイヤ、野生のカルチョーフィは、取材先から持ち帰った現地の味。
野生のカルチョーフィは、鋭い棘の皮を剥くのが大変な作業。地元でもそれをやる人が減っている。
Antipasti 1
Carpaccio di pesce marinato al pomodoro e bergamotto
白身魚のカルパッチョ トマトとベルガモット風味
すみません写真ないですが、ベルガモット風味がカラブリア風。ベルガモットはレッジョ・ディ・カラブリアの特産品。
Antipasti 2
Crocchette di melanzane,melanzane marinato alla menta
ナスのコロッケと、ナスのミントマリネ
ナスの季節はナス料理責め。色々なレシピがある。
Primo
Fileja con peperoni e cruschi alla rosamarina
パプリカ、クルスキ、ローザマリーナの自家製フィレイヤ
カラブリアらしいパスタ! 生シラスの唐辛子漬けローザマリーナ。発酵具合がいい。
Second
Polpetta ripieni di n’duja al forno arrotolati con foglie di fico
イチジクの葉で包んだポルペッテのオーブン焼き ンドゥイヤ風味
イチジクの甘い風味と、ピリ辛のンドゥイヤのハーモニー。カラブリアにはイチジクの名産地がある。
Dolce
Tartufo di Pizzo
ピッツォのタルトゥーフォ
トリュフではありません。ピッツォ・カラブロという町の名物、タルトゥーフォの形をしたジェラート。地元では大人も夢中。
柳さんのカラブリア愛の溢れる料理に満腹、満足でした!
カラブリアに行かずとも、カラブリア気分満タン。
でも、行ったらもっといいんです。
柳さん、赤松さん、福田さん、そして参加者の皆さんありがとうございました。