魅力ある村は本当にたくさんありますが、その中でもとくに珍しい水のせせらぎを村のいたるところで楽しめる小さな村・ラシーリアと、花で飾られた町角が魅力いっぱいの花の町・スペッロをご紹介いたします。
豊かなメノートレ川の水源に恩恵を受け、美しいせせらぎの姿を村のいたるところで見せてくれるウンブリア州フォリーニョ県の小さな村、ラシーリア。ペルージャからも26㎞強とそう遠くなく、ウンブリア州のほぼ真ん中に当たる位置にある、住人が50人にも満たない小さな村です。中世の面影を残した村は、古くから商人が利用していたローマとアンコーナをつなぐ街道からも隣接し、自治権が与えられていた立派な商業の村でした。
自然のせせらぎとともにいくつも造られた水路は、村中を血管のようにめぐっており、羊毛加工や天然染色、水力を活かした粉挽きが盛んで、いくつもの石臼の粉挽き小屋があったそうです。水を求め住み着いた人々によって支えられた産業により経済的な発展があったものの、第二次世界大戦後は手仕事の衰退で、染色や織物に勤しんだ人々の姿は過去のものとなってしまいました。
ですが、その村の独特な造りと清らかなせせらぎの魅力は消えることなく現在もとどまっており、沢山の来訪者を魅了しています。とくに水の美しさと透明感を引き立てるのは、水中に育つ植物たち。濁りの一切無いクリスタルのような水の中には、さしずめ水中の庭と呼べるようなグリーンが広がり、さわやかさを一層引き立ててくれます。
次にご紹介するのはラシーリアからアッシジ方面に25㎞ほど移動した位置にあるスペッロ。 ペルージャ県にある人口約8600人この町は“イタリアの最も美しい村”にも登録されています。
アペニン山脈の西側、スバジオ山のふもとに広がる中世の町並みの残る美しい古都ですが、この町の歴史はイタリアでも最も古い民族と言われているウンブロ族によって切り開かれた、と言われているほど歴史が古く、サンタ・マリア・マッジョーレ教会にあるピントゥリッキォによるフレスコ画をはじめ、多くの教会、美術作品が見られる文化の町でもあります。
この街の大きな特徴は、住人全体が花による町の装飾にとても力を入れていること。中世の町並みのいたる所に美しく植えられた草花は町をいっそう魅力的なものにし、自治体はより魅力的に設えられたテラスには賞を与えるという、ユニークなコンテストも開催しています。このコンテストのおかげで町は市民によって花々で飾られ、住む人も訪れる人も喜ばしいという相乗効果が生まれています。その美しい町角をモチーフにしようと訪れる写真家や画家の方々も少なくないそうですよ。
そしてスペッロの代表的な花の行事といえば、インフィォラータ!
これはイタリアではキリストの聖体祭といわれるカトリックのお祭りに合わせて作られるフラワーカーペットのこと。復活祭から50日後のペンテコステまたは五旬節のあとの日曜日(多くは6月第3または第4日曜日)が聖体祭と定められているので、毎年変動します。
お祭り当日に向けて何日もかけて大量の花びらが摘まれ、下絵に合わせて各色の花びらが並べられていき、フラワーカーペットとなります。これが風で飛んでしまわないよう大型のテントが張られ、お祭り当日にのみテントが取り除かれますが、その瞬間にあがる大歓声で観客の感動が伝わります。
イタリアでは沢山の町でこのインフィォラータが行われますが、スペッロで行われるインフィォラータは、花の町と呼ばれているだけあり、お見事! 素敵な町並みの中に、それはそれは美しいフラワーカーペットを見ることができます。町中が花に溢れるこの季節は、初夏の陽気と住民の活気と共にとにかく町中から花の恩恵を受けられる、本当に素敵なイベントです!
花のお好きな方にはぜひ足を運んでいただき、花の陽気に包まれて思い切り深呼吸をしてほしい、そんな場所なのです。
●HP:https://www.infiorataspello.it/infiorate-2022//
●instagram:https://www.instagram.com/infioratespello/





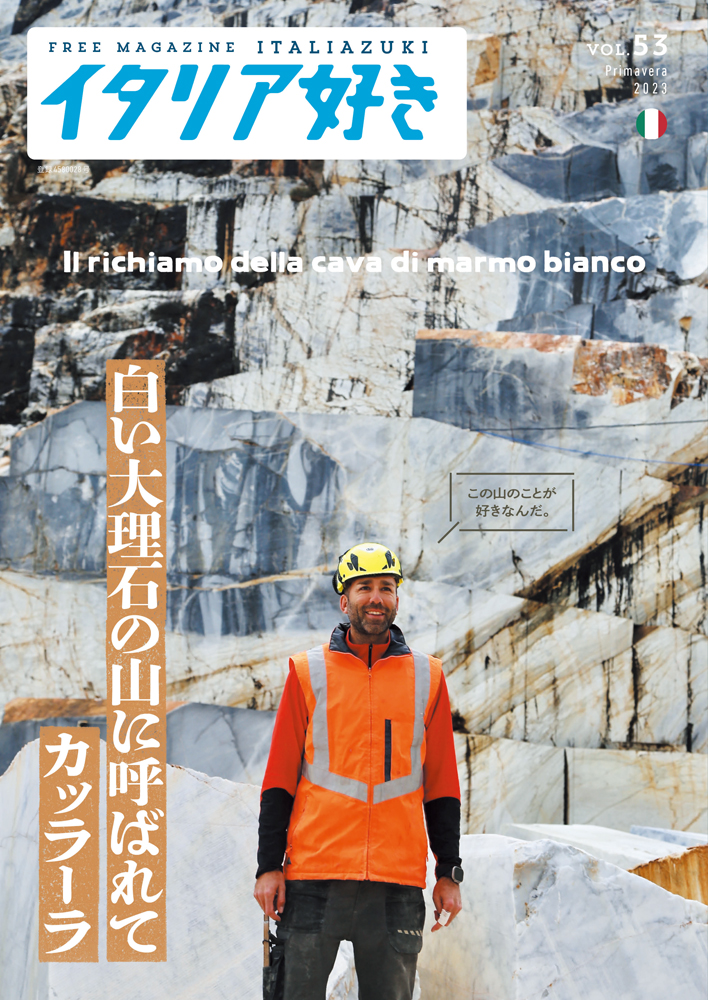





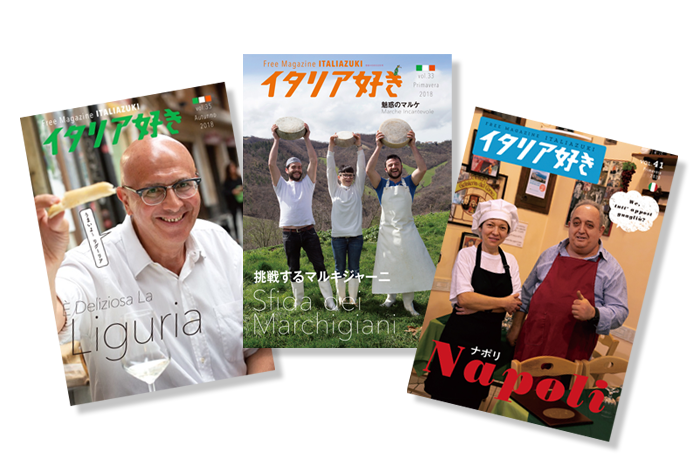
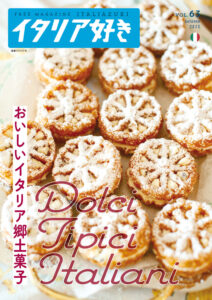
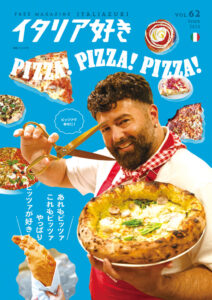

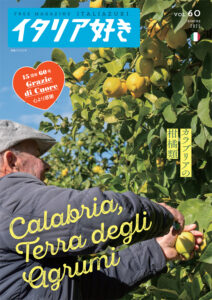



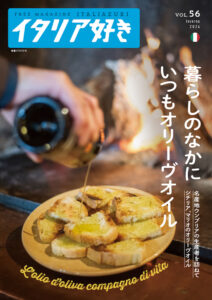

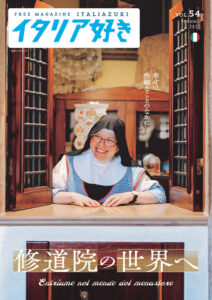
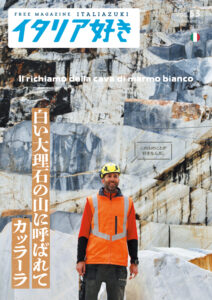


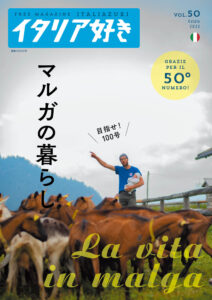
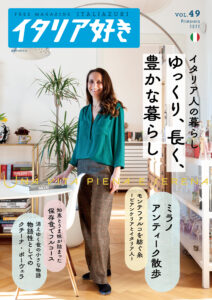
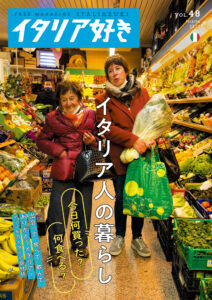

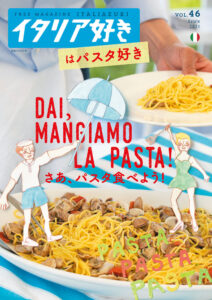

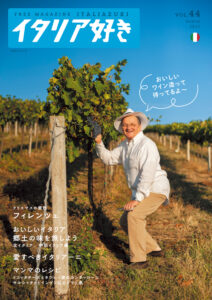
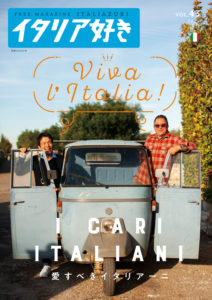
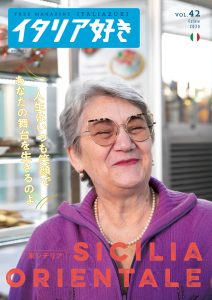

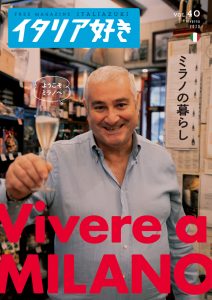
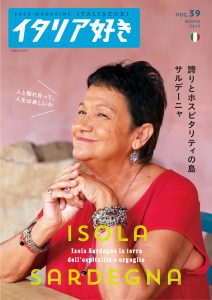
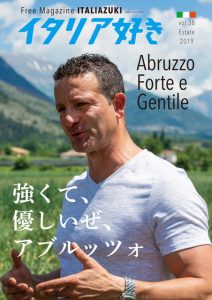
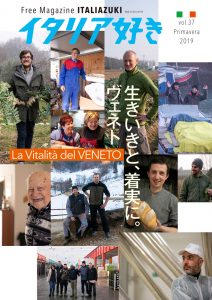
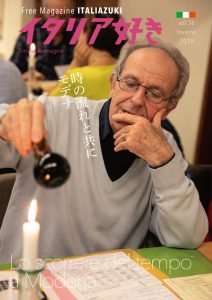


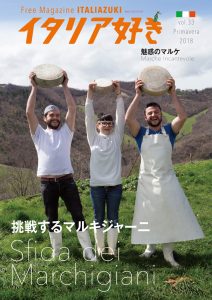

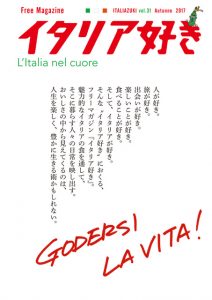


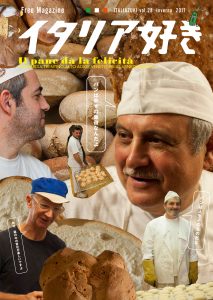
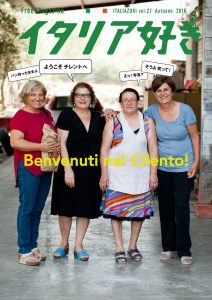
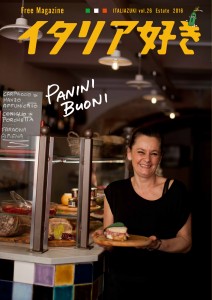





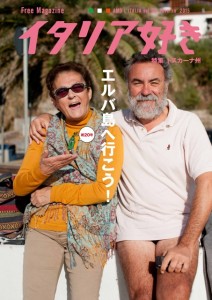
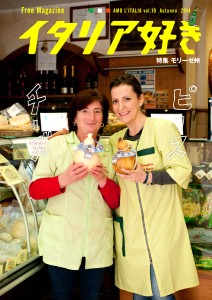
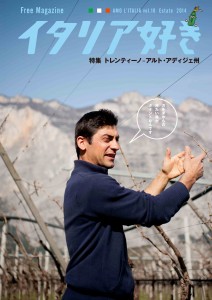


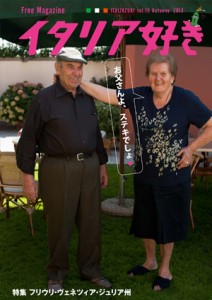

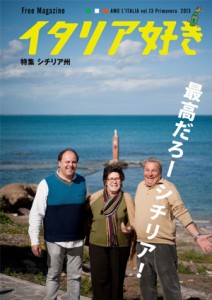

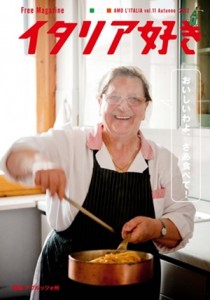

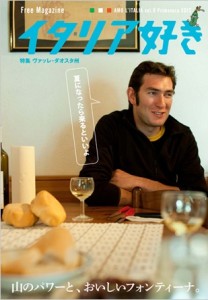


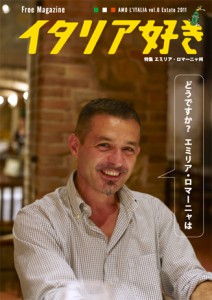


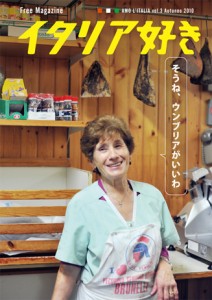
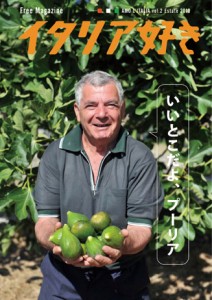

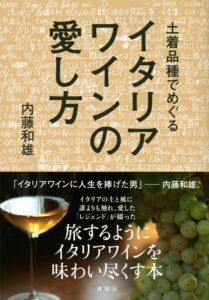
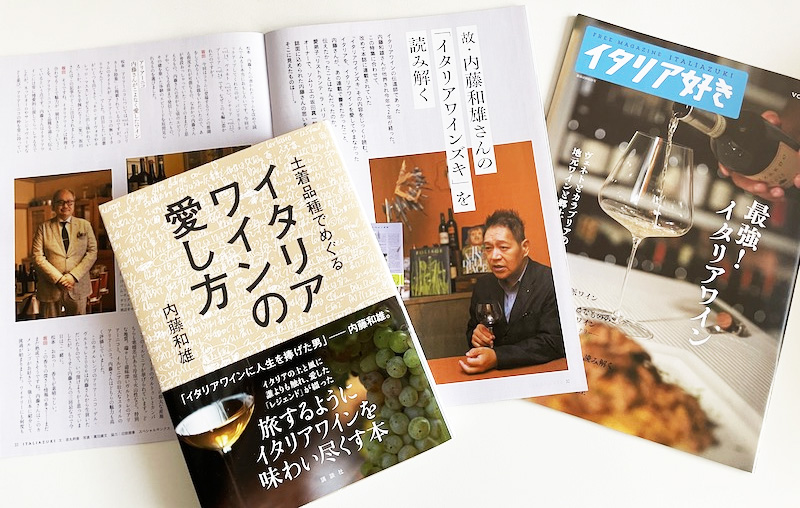

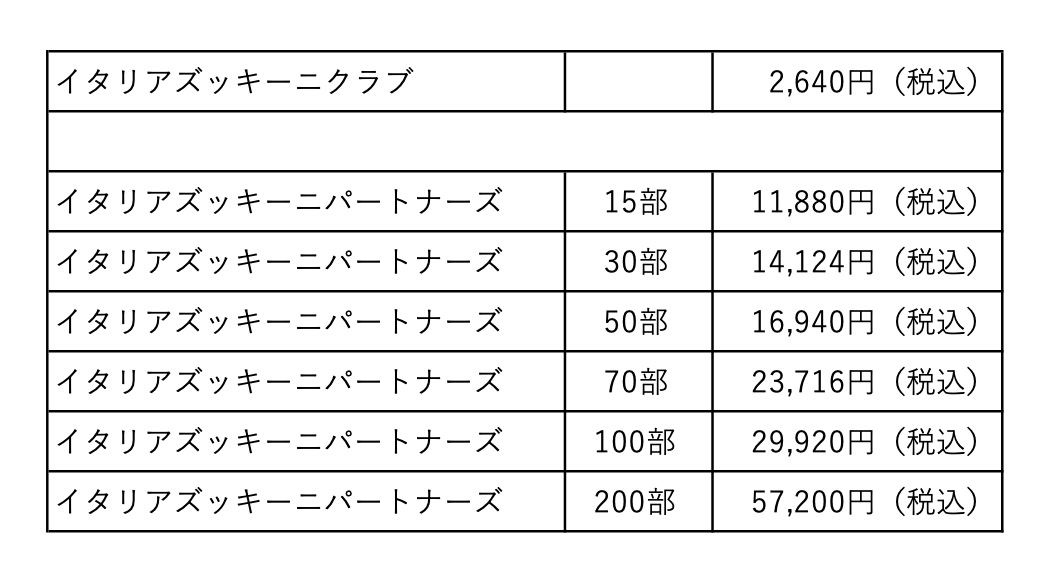




 本誌連載としてvol.51から始まった「イタリアでトレイルを走る」では、トレイルランニングとTor des Geantsを取り上げ、その魅力を紹介しています。
本誌連載としてvol.51から始まった「イタリアでトレイルを走る」では、トレイルランニングとTor des Geantsを取り上げ、その魅力を紹介しています。

























