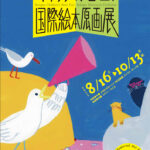イタリア北部に位置するヴェネト州は、長く寒い冬の真っ最中。寒い土地柄であるがゆえの食材が非常に豊富で、冬らしいおいしいものが満載の時期ともいえます。メルカートを一回りして、季節を感じてみましょう。
「冬の華」と別名を持つ、ラディッキオ

ラディッキオはヴェネト州の冬野菜の代表選手で、チコリの仲間。鮮やかな赤紫色と白色とのコントラストが目をひきます。州内各地で異なる品種のラディッキオが存在し、それぞれの土地の名前がついています。
そのなかでも特殊なのが、トレヴィーゾ産ラディッキオです。これには、先の尖った円すい状の形をしたプレコーチェ(早生)種と、筆のような形が特徴のタルディーヴォ(晩生)種があります。特に後者のものは、見た目にも非常に印象の強いものです。
生産工程も特殊。出荷前に一度、根を地下水の流れる流水プールに浸し、軟白工程をとります。こうすることで鮮やかな色を強調させ、口当たりのコリッとした食感(クロッカンテと表現します)が出てきます。
その他、丸いボール形のキオッジャ産、淡い緑黄色に紫色の斑点の入ったカステルフランコ産、トレヴィーゾ産よりも小さめなヴェローナ産、淡いピンク色のローザというものもあります。
珍しい品種のブロッコリー。風味豊かな冬の珍品

ブロッコリーやカーヴォロ(キャベツ)類の野菜は、イタリア各地やほかにも有名な産地があり、それぞれの土地の郷土料理とつながりが深いものです。ヴェネト州、ヴィツェンツァ県の西側にクレアッツォという小さな地域があり、この小さな地区のみで生産されるのが、「ブロッコリー・フィオラーロ」と呼ばれるブロッコリーの品種です。
「フィオラーロ」というのは、主株から子株をどんどんと数多くのばしていくこと(インフィオレシェンツェ)から。この子株は「フィーリ(子ども)」と俗称されており、それが地元の訛りで「フィオーイ」と呼ばれていることに由来します。長い茎の部分も食べることができます。ゆでてオイルとレモンをかけたり、リゾットやパスタに入れたり……など、冬ならではの滋養のあるおいしい野菜です。
バッカラ料理は冬が本番!

ヴェネト料理の代表素材ともいえるのが、バッカラ(タラの一種である大型の白身魚・メルルーサを干したもの)です。ただし、ヴェネトで主用されるのは、実はバッカラではなく、ストッカフィッソといいます。地元の人でも混同してしまうのですが、前者は3枚におろして塩漬けしたもの、後者は内臓を取り除き、寒風干しにしたものです。
これはヴェネツィア商人が航海の際に北欧から持ち帰ったもので、ヴェネト州内には古くから、非常に根強く普及しています。バッカラ・マンテカート(ゆでたバッカラにオイルを加えながらかくはんし、パテ状に仕上げるヴェネツィア料理)、バッカラ・アッラ・ヴィツェンティーナ(タマネギやアンチョビ、そしてたっぷりの牛乳、オイル、おろしたグラーナを加えて長時間煮込んだ、ヴェネトの内陸であるヴィツェンツァが発祥の料理)などが代表的な料理として知られています。
肉質がしっかりとした魚で、夏場よりもどちらかというと冬場に煮込みなどで使われる機会が多いもの。戻す際には時間もかかり(最低3日間要する)、バッカラ特有の匂いも強いので、家庭で戻すよりもすでに戻したものを購入する主婦も珍しくありません。冬期には、ほとんどの魚屋の店先で水で戻したものが売られます。
このように、冬ならではの力強い食材たちが、それぞれの特色を存分にアピールしながら店頭にならんでいます。実際にメルカートを歩いてみると、それが実感できるはずです。寒い冬のヴェネトの食材探求に、ぜひいらしてください!
(2019年2月)