イタリア好き読者の皆様 いまさらですが、あけましておめでとうございます。今年もカンパーニア州をよろしくお願いいたします。
果報は寝て待て。
待った甲斐があり、ご縁があって、”卓越したカゼルタ県の食のショークッキング”へ参加させて頂きました。カンパニアと言えば、カプリやアマルフィ、ナポリばかりのクローズアップで、海のイメージが強いのですが、今回は海から離れ内陸へ。本誌でも2度ほど取材させて頂いた、チレントも未知のカンパニーア州ですが、このカゼルタ県もカンパーニア州5県の一つで、王宮は有名ですがそれ以外の場所は馴染みがない方が大半だと思います。偉そうに言っていますが、カゼルタ県は、私もほぼノーマークゾーンでした。
 ◆昨年Caiati 15’にて悲願のトレビキ獲得。ワイナリALOISのオーナーミケーレさん◆
◆昨年Caiati 15’にて悲願のトレビキ獲得。ワイナリALOISのオーナーミケーレさん◆
ナポリ一帯は、1738年ウィーン条約からカルロ5世となりナポリ支配が始まります。
歴史の話はうっとおしいのですが、ナポリが栄華を極めた時代、カンパニーア人にとってのベルエポック(良き時代)な訳で、ナポリ人の家には下手すると、イタリアの国旗より、両シチリア王国の旗があったりします。

 ◆こんなに遠くまで降ってきた、ベスビオ火山灰の堆積層◆
◆こんなに遠くまで降ってきた、ベスビオ火山灰の堆積層◆
今となっては信じられませんが、ナポリは欧州の重要都市としてのフランスのパリ同様の文化レベルと地位を築きました。そんなブルボン王朝の王様は、政治以外にもいろいろやっていたんだな~と、カルロ5世と息子のフェルディナンド1世が、妙に身近に感じたワークショップでした。カゼルタ県の北内陸、ラッツィオ州に近いロッカモンフィーナ、マテーゼとの迫にあるポンテラトーネには、あのベスビオから降ってきた火山灰の体積層からなる、土壌があります。
 ◆ピエトロ・レオネッティ氏 子羊の炭火焼、生後2~3か月のとても小さな羊◆
◆ピエトロ・レオネッティ氏 子羊の炭火焼、生後2~3か月のとても小さな羊◆
ナポリがブルボン朝支配の時代(日本はどっぷり江戸時代)に、ここカゼルタ王宮の後方には、カルロ5世の息子、フェルディナンド1世が推し進めたプロジェクトで絹織物工場を核とした理想郷、サンレウチョの町が広がります。日本人観光客の方々が、ほぼ皆さんスルーですが、ここもユネスコの世界遺産なのです。手つかずだったこの地に王は、大ギリシャ時代から伝わる土着品種のパラグレッロ・ビアンコ、パラグレッロ・ネーロ、カーサヴェッキアというような苗を積極的に栽培したり、今回のショークッキングでもメニューに上がった、羊の飼育も推進したそうです。ブルボン朝支配下時代からつけ継がれるこのの羊は、臭みが尻尾に集積しやすい品種で、実際、羊独特のにおいは一切しませんでした。
 ナポリが芸術と政治の中心だとすれば、この一帯は、ブルボン家の産業の核になっていたのかもしれないなぁ~。
ナポリが芸術と政治の中心だとすれば、この一帯は、ブルボン家の産業の核になっていたのかもしれないなぁ~。
250年以上前から受け継がれる羊の品種の肉を食べて、土着品種のワインを飲んでみると、「あっ、王様、こんにちは! ものすごいセレクトで攻めましたね、21世紀でも全然行けてますぅ~」と言いたくなるぐらい身近に感じてしまう。。
 ◆ミシュランスターシェフのレナート・マルティーノ氏のショー◆
◆ミシュランスターシェフのレナート・マルティーノ氏のショー◆
ブルボンパワーの次には、水牛肉のカルパッチョ。カゼルタ県はモッツァレッラチーズの産地ですが、その水牛の【乳】ではなく、【肉】です。やっぱり、ミシュラ~ンのスターシェフによる魔法がかかると、ただの焼肉ではなくなりますね。まさかのクルード(生)にオリジナルの味付けであっさり!前菜からおかわり!してしまいました。こちらも臭みゼロ。
 ◆ジュゼッペ・イアコネッリ氏 チーズ作りはフランスから学んだ部分が多いそうです◆
◆ジュゼッペ・イアコネッリ氏 チーズ作りはフランスから学んだ部分が多いそうです◆
そして私が興味を持ったのは、凝乳酵素を一切使わないチーズCandida。チーズの始まりはそもそも、牛乳が温度により発酵し始め、少し凝固した感じ?発酵過程において、マルサラ酒で少し風味付けをしているチーズで、この生きた食品は、日本の豆腐に通じるものがある。マルサラがチーズの発酵で何となく味噌麹のような味わいになったもろみ風のチーズでした。
 ◆フランコ ペペ氏 揚げ、窯と2種類づつを披露◆
◆フランコ ペペ氏 揚げ、窯と2種類づつを披露◆
そして昨年度、Pizza50のコンクールで、ナンバーワンに輝いたフランコ氏のピッツァ。ここ数年でナポリピッツァはずいぶん変わってきましたので、その最先端ピッツァとでも申しましょうか?生地が軽く、胃にもたれない。トッピングの素材には厳選をした地元の素材を使用しています。ワークショップ前日に、お店の方へもお邪魔しましたが、最近のナポリピッツァを知らない方が食べたらびっくりするようなヘルシー感にあふれています。
今回のワークショップメーカーは、
ワイナリ:ALOIS
料理:Ristorante Vairano del Volturno
肉:Ristorante Frantoio Ducale
パスタ:Pastificio Gerardo di Nola
ピッツァ:Pizzeria Pepe in Grani
チーズ:Optimum Sancti Petri
でした。各メーカーの皆さま、ありがとうございました。
ナポリと近郊の最新情報はBLOG【ナポリのテラスから】 をご覧ください。
南イタリア、ナポリ市内の交通や観光ツアー情報他は【Piazza Italia】サイトをご覧ください。
果報は寝て待て。
待った甲斐があり、ご縁があって、”卓越したカゼルタ県の食のショークッキング”へ参加させて頂きました。カンパニアと言えば、カプリやアマルフィ、ナポリばかりのクローズアップで、海のイメージが強いのですが、今回は海から離れ内陸へ。本誌でも2度ほど取材させて頂いた、チレントも未知のカンパニーア州ですが、このカゼルタ県もカンパーニア州5県の一つで、王宮は有名ですがそれ以外の場所は馴染みがない方が大半だと思います。偉そうに言っていますが、カゼルタ県は、私もほぼノーマークゾーンでした。
 ◆昨年Caiati 15’にて悲願のトレビキ獲得。ワイナリALOISのオーナーミケーレさん◆
◆昨年Caiati 15’にて悲願のトレビキ獲得。ワイナリALOISのオーナーミケーレさん◆ナポリ一帯は、1738年ウィーン条約からカルロ5世となりナポリ支配が始まります。
歴史の話はうっとおしいのですが、ナポリが栄華を極めた時代、カンパニーア人にとってのベルエポック(良き時代)な訳で、ナポリ人の家には下手すると、イタリアの国旗より、両シチリア王国の旗があったりします。

 ◆こんなに遠くまで降ってきた、ベスビオ火山灰の堆積層◆
◆こんなに遠くまで降ってきた、ベスビオ火山灰の堆積層◆今となっては信じられませんが、ナポリは欧州の重要都市としてのフランスのパリ同様の文化レベルと地位を築きました。そんなブルボン王朝の王様は、政治以外にもいろいろやっていたんだな~と、カルロ5世と息子のフェルディナンド1世が、妙に身近に感じたワークショップでした。カゼルタ県の北内陸、ラッツィオ州に近いロッカモンフィーナ、マテーゼとの迫にあるポンテラトーネには、あのベスビオから降ってきた火山灰の体積層からなる、土壌があります。
 ◆ピエトロ・レオネッティ氏 子羊の炭火焼、生後2~3か月のとても小さな羊◆
◆ピエトロ・レオネッティ氏 子羊の炭火焼、生後2~3か月のとても小さな羊◆ナポリがブルボン朝支配の時代(日本はどっぷり江戸時代)に、ここカゼルタ王宮の後方には、カルロ5世の息子、フェルディナンド1世が推し進めたプロジェクトで絹織物工場を核とした理想郷、サンレウチョの町が広がります。日本人観光客の方々が、ほぼ皆さんスルーですが、ここもユネスコの世界遺産なのです。手つかずだったこの地に王は、大ギリシャ時代から伝わる土着品種のパラグレッロ・ビアンコ、パラグレッロ・ネーロ、カーサヴェッキアというような苗を積極的に栽培したり、今回のショークッキングでもメニューに上がった、羊の飼育も推進したそうです。ブルボン朝支配下時代からつけ継がれるこのの羊は、臭みが尻尾に集積しやすい品種で、実際、羊独特のにおいは一切しませんでした。
 ナポリが芸術と政治の中心だとすれば、この一帯は、ブルボン家の産業の核になっていたのかもしれないなぁ~。
ナポリが芸術と政治の中心だとすれば、この一帯は、ブルボン家の産業の核になっていたのかもしれないなぁ~。250年以上前から受け継がれる羊の品種の肉を食べて、土着品種のワインを飲んでみると、「あっ、王様、こんにちは! ものすごいセレクトで攻めましたね、21世紀でも全然行けてますぅ~」と言いたくなるぐらい身近に感じてしまう。。
 ◆ミシュランスターシェフのレナート・マルティーノ氏のショー◆
◆ミシュランスターシェフのレナート・マルティーノ氏のショー◆ブルボンパワーの次には、水牛肉のカルパッチョ。カゼルタ県はモッツァレッラチーズの産地ですが、その水牛の【乳】ではなく、【肉】です。やっぱり、ミシュラ~ンのスターシェフによる魔法がかかると、ただの焼肉ではなくなりますね。まさかのクルード(生)にオリジナルの味付けであっさり!前菜からおかわり!してしまいました。こちらも臭みゼロ。
 ◆ジュゼッペ・イアコネッリ氏 チーズ作りはフランスから学んだ部分が多いそうです◆
◆ジュゼッペ・イアコネッリ氏 チーズ作りはフランスから学んだ部分が多いそうです◆そして私が興味を持ったのは、凝乳酵素を一切使わないチーズCandida。チーズの始まりはそもそも、牛乳が温度により発酵し始め、少し凝固した感じ?発酵過程において、マルサラ酒で少し風味付けをしているチーズで、この生きた食品は、日本の豆腐に通じるものがある。マルサラがチーズの発酵で何となく味噌麹のような味わいになったもろみ風のチーズでした。
 ◆フランコ ペペ氏 揚げ、窯と2種類づつを披露◆
◆フランコ ペペ氏 揚げ、窯と2種類づつを披露◆そして昨年度、Pizza50のコンクールで、ナンバーワンに輝いたフランコ氏のピッツァ。ここ数年でナポリピッツァはずいぶん変わってきましたので、その最先端ピッツァとでも申しましょうか?生地が軽く、胃にもたれない。トッピングの素材には厳選をした地元の素材を使用しています。ワークショップ前日に、お店の方へもお邪魔しましたが、最近のナポリピッツァを知らない方が食べたらびっくりするようなヘルシー感にあふれています。
今回のワークショップメーカーは、
ワイナリ:ALOIS
料理:Ristorante Vairano del Volturno
肉:Ristorante Frantoio Ducale
パスタ:Pastificio Gerardo di Nola
ピッツァ:Pizzeria Pepe in Grani
チーズ:Optimum Sancti Petri
でした。各メーカーの皆さま、ありがとうございました。
ナポリと近郊の最新情報はBLOG【ナポリのテラスから】 をご覧ください。
南イタリア、ナポリ市内の交通や観光ツアー情報他は【Piazza Italia】サイトをご覧ください。


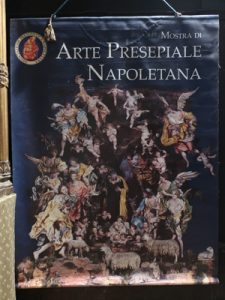






 カルメーラ! 前回のイタリア好きの主人公です!
カルメーラ! 前回のイタリア好きの主人公です! オリーブオイルメーカーのPietrabianca。この時期、当たり前ですが一分たりとも隙間なしの過密スケジュールをこなすジェルマーノさん。自社ブランドの収穫はほぼ終了。機械がフル稼働でうるさいので、耳にヘリ用の騒音よけをつけています(笑)。会話がかなり成立しにくかったです。
オリーブオイルメーカーのPietrabianca。この時期、当たり前ですが一分たりとも隙間なしの過密スケジュールをこなすジェルマーノさん。自社ブランドの収穫はほぼ終了。機械がフル稼働でうるさいので、耳にヘリ用の騒音よけをつけています(笑)。会話がかなり成立しにくかったです。 生まれたてのオイルは真緑のどっろどろです。濾過する前だから、濁っています。
生まれたてのオイルは真緑のどっろどろです。濾過する前だから、濁っています。 そして、豆農家のミケーレさん。息子さんのアンジェロさんも一緒に!
そして、豆農家のミケーレさん。息子さんのアンジェロさんも一緒に!















