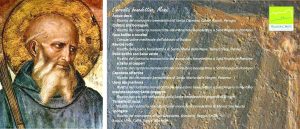皆さんこんにちは!
今日は、ちょっと(凄く)嬉しいお知らせが
マルケ州の食をこよなく愛する友人たちと長年温めていた企画、マルケの食文化を発信するアソシエーション”マッカ•ローニ”が遂に去年の末から発足しました!
発起人は私を含む10人前後のメンバーで、郷土料理研究家であり、こちらイタリア好きさんで紹介させて頂いたマンマのレシピのフランチェスカ、アンナの他に食の歴史家の方や生産者さんなどなどバラエティーに富んだメンバー。我らが基地はここウルバーニア、マルケ州北部の美しい小さな街であり、かつてカステルドウランテと呼ばれたマヨリカ焼きの有数の産地でもあった歴史深いこの街。ウルビーノを中心としたモンテフェルトロ領でもあることから、文化、芸術、歴史がクロスする私の中での小さなパワースポットなんです。
 こちらは先日あったアソシエーションがオーガナイズしたワークショップの様子。今日のテーマは”チーズを使った料理を楽しむ”でした。
こちらは先日あったアソシエーションがオーガナイズしたワークショップの様子。今日のテーマは”チーズを使った料理を楽しむ”でした。
 そうそう、私たちの本部はアンナさんの経営するB&B,ムリーノ•デッラ•リカバータ(Mulino della ricavata)。文化財にもなっている川の水力でかつて粉を挽いていた小屋を改造して作った素晴らしい建物。建物がテレビでも紹介されるなど、見学するだけでも価値のある文化的建造物なんです。
そうそう、私たちの本部はアンナさんの経営するB&B,ムリーノ•デッラ•リカバータ(Mulino della ricavata)。文化財にもなっている川の水力でかつて粉を挽いていた小屋を改造して作った素晴らしい建物。建物がテレビでも紹介されるなど、見学するだけでも価値のある文化的建造物なんです。
 こちらがその建物の内部。一部小さな鍾乳洞のようになっている空間にオリーブを挽くための石臼と小麦を挽くための石臼が一室に両方並んでいる珍しい例でもあります。
こちらがその建物の内部。一部小さな鍾乳洞のようになっている空間にオリーブを挽くための石臼と小麦を挽くための石臼が一室に両方並んでいる珍しい例でもあります。
 さて、ワークショップの楽しそうな様子も紹介していきましょう。
さて、ワークショップの楽しそうな様子も紹介していきましょう。
今日の参加者は若いカップルから年配のおばちゃんたちまで様々皆興味津々でじっくりと手順を見ています。先生はもちろんアンナとフランチェスカ。
それぞれレシピ本を出版していたりと地元では食のエキスパートの二人。この二人と出会ったことで、食文化の素晴らしさや大切さに目覚めたと言っても過言ではない、大切な友人です。
 いつでも真剣に、でもお茶目にお話をするフランチェスカ。お惣菜店を家族で経営しながら歴史深い郷土食を研究しています。マンマのレシピでも数回登場してくれました。
いつでも真剣に、でもお茶目にお話をするフランチェスカ。お惣菜店を家族で経営しながら歴史深い郷土食を研究しています。マンマのレシピでも数回登場してくれました。
 多くのレシピを研究し、ごく最近までアグリを経営していたことからお料理の腕はお墨付き、海外にもファンの多いアンナさん。私とはハーブ好きの仲間でもあります
多くのレシピを研究し、ごく最近までアグリを経営していたことからお料理の腕はお墨付き、海外にもファンの多いアンナさん。私とはハーブ好きの仲間でもあります
🌿。
そもそも、なぜ私たちのアソシエーションがMac caroniという名前なのかちょっとお話しましょう。
時代は第2次世界大戦後、イタリアも参戦した国の1つですが、戦後のイタリアは職が無く多くのイタリア人は仕事を求めて海外へ。海外へ行けどやはり血はイタリア人、食べるものと言えばパスタ、パスタ、そしてパスタ(笑)だったそうです。当時は時代柄あまり学がなかった田舎出身の労働者も多く、そんなパスタばかり食べ田舎者的な振る舞いをしていたイタリア人たちは、総合的なパスタの別名、マッカローニばかりを食べる人種として、ちょっとした中傷的な意味も含めて食べ物そのものの名前で呼ばれていたのです。
そんな時代に想いを馳せた時、確かにこのような時代はあったにせよ、田舎で生まれたミクロテリトリー的な食文化や無数のマンマのレシピは今のイタリア食のべースになっていることは紛れもない真実ですから、そんな貧しい時代のイタリアから仕事を求めて移民として移住し、図らずも食の風習を継承していった多くの人々に敬意を払うと同時に、埋もれつつある食に光を当てたい、文化としての食にふれ合う機会を作りたい、という気持ちからこのマッカローニという名前が生まれました。
さて、ワークショップに話を戻しましょう。
チーズがテーマの食材だったこの回、どんなお料理を作ったのかご紹介しましょう。

こちらは3種の前菜、3色の野菜(インゲン、根セロリ、ニンジン)のテリーヌ、カショッタ•デイ•ウルビーノというチーズのラデイッキョ巻き、鶏肉のサラダのゴルゴンゾーラソース。どれもさっぱりとしていながらチーズの濃厚な美味しさは存在感があり、思わずおかわりしてしまいます😆。
 これがカショッタ•デイ•ウルビーノというチーズです。かのミケランジェロのお気に入りのチーズとして注文したという1545年付けの文書が残っており、DOPも獲得した牛乳と羊乳半々で作られた歴史の深いチーズです。
これがカショッタ•デイ•ウルビーノというチーズです。かのミケランジェロのお気に入りのチーズとして注文したという1545年付けの文書が残っており、DOPも獲得した牛乳と羊乳半々で作られた歴史の深いチーズです。
 こちらはカプリーノというヤギのお乳のチーズを使った爽やかな1品。紫ビートの汁で作ったジュレを乗せて色鮮やかに。
こちらはカプリーノというヤギのお乳のチーズを使った爽やかな1品。紫ビートの汁で作ったジュレを乗せて色鮮やかに。
 そしてこの不思議なパスタはこの日のメニューの主役です!
そしてこの不思議なパスタはこの日のメニューの主役です!
パスタ•アル•サッコと呼ばれるこの1品。
その名の通り、イタリア語では”袋のパスタ”。
そう、このパスタ、チーズと小麦粉、卵を混ぜた生地を布袋に入れて、直接スープの中で煮るというとても珍しいパスタなんです。
 生地をよーく混ぜて…
生地をよーく混ぜて…
 清潔な木綿の袋に入れます。
清潔な木綿の袋に入れます。
 しっかりと紐で袋を結び、
しっかりと紐で袋を結び、
 鶏と野菜たっぷりのスープにポン!笑。
鶏と野菜たっぷりのスープにポン!笑。
 あとは1時間ほど煮込みます。
あとは1時間ほど煮込みます。
このパスタは今ではすっかり作る人が減ってしまったいわゆる幻のパスタ。
今60代以上の方は小さい頃に良く食べたわー、とお話ししてくれましたが、私も見たのは今日がはじめて。
少しの生地でもスープをタップリ吸って膨らむので、家族の多かった農家などでは重宝されていたレシピだったそうです。これも僅かな食材でいかに家族全員のお腹を一杯にするかの工夫から生まれたものなのよ、とおしゃべりも弾みます🎵
 さて煮終わったパスタは袋から出されます。
さて煮終わったパスタは袋から出されます。
固まりになってゴロリ。
 これをこうしてキューブ状に切って煮るのに使ったスープに戻します。
これをこうしてキューブ状に切って煮るのに使ったスープに戻します。
 こんな風に素敵な1品に💕
こんな風に素敵な1品に💕
南マルケのマチェラータでは、このパスタを3色に分けて作るそうで、スープに綺麗に映えるとか。それは是非やってみたい!と叫ぶ私•笑。
 一気にたくさん作ったので、皆さんちょっと一息。
一気にたくさん作ったので、皆さんちょっと一息。
暖炉の炎の暖かさがゆるりとした空気を作り出してくれます。
 デザートはプリンの原型と言われているラッタローロというお菓子。みんなフランチェスカの話を真剣に聞いています。
デザートはプリンの原型と言われているラッタローロというお菓子。みんなフランチェスカの話を真剣に聞いています。
こちらはチーズは入っていませんが昔からの農家の贅沢おやつとして紹介。レシピの歴史が大好きなフランチェスカ、彼女の昔のお話と絡めながら作っているとポピュラーなプリンも奥深いお菓子だと言うことに気着くのです。
 型から無事に出てきてくれました。
型から無事に出てきてくれました。
 スープを取った鶏肉もまだまだ旨味が残っています。
スープを取った鶏肉もまだまだ旨味が残っています。
細かく裂いて、オレンジとゴルゴンゾーラソースのサラダに。スミレの甘い香りが一杯の大変美味なサラダでした。
 こんな風に和気あいあいと終わったワークショップ。
こんな風に和気あいあいと終わったワークショップ。
このアソシエーションが発足したのをきっかけに、これからも仲間たちと文化、食、歴史と芸術も絡めつつ面白い企画をたくさん紹介していければと思います。
共に過ごす、共に食することも料理を完成するエッセンスとして大切にする、Conviviale という素晴らしい言葉。この言葉をキーワードとしてまた色々なイベントを紹介していきますね。
それでは、また!😊
今日は、ちょっと(凄く)嬉しいお知らせが
マルケ州の食をこよなく愛する友人たちと長年温めていた企画、マルケの食文化を発信するアソシエーション”マッカ•ローニ”が遂に去年の末から発足しました!
発起人は私を含む10人前後のメンバーで、郷土料理研究家であり、こちらイタリア好きさんで紹介させて頂いたマンマのレシピのフランチェスカ、アンナの他に食の歴史家の方や生産者さんなどなどバラエティーに富んだメンバー。我らが基地はここウルバーニア、マルケ州北部の美しい小さな街であり、かつてカステルドウランテと呼ばれたマヨリカ焼きの有数の産地でもあった歴史深いこの街。ウルビーノを中心としたモンテフェルトロ領でもあることから、文化、芸術、歴史がクロスする私の中での小さなパワースポットなんです。
 こちらは先日あったアソシエーションがオーガナイズしたワークショップの様子。今日のテーマは”チーズを使った料理を楽しむ”でした。
こちらは先日あったアソシエーションがオーガナイズしたワークショップの様子。今日のテーマは”チーズを使った料理を楽しむ”でした。 そうそう、私たちの本部はアンナさんの経営するB&B,ムリーノ•デッラ•リカバータ(Mulino della ricavata)。文化財にもなっている川の水力でかつて粉を挽いていた小屋を改造して作った素晴らしい建物。建物がテレビでも紹介されるなど、見学するだけでも価値のある文化的建造物なんです。
そうそう、私たちの本部はアンナさんの経営するB&B,ムリーノ•デッラ•リカバータ(Mulino della ricavata)。文化財にもなっている川の水力でかつて粉を挽いていた小屋を改造して作った素晴らしい建物。建物がテレビでも紹介されるなど、見学するだけでも価値のある文化的建造物なんです。 こちらがその建物の内部。一部小さな鍾乳洞のようになっている空間にオリーブを挽くための石臼と小麦を挽くための石臼が一室に両方並んでいる珍しい例でもあります。
こちらがその建物の内部。一部小さな鍾乳洞のようになっている空間にオリーブを挽くための石臼と小麦を挽くための石臼が一室に両方並んでいる珍しい例でもあります。 さて、ワークショップの楽しそうな様子も紹介していきましょう。
さて、ワークショップの楽しそうな様子も紹介していきましょう。今日の参加者は若いカップルから年配のおばちゃんたちまで様々皆興味津々でじっくりと手順を見ています。先生はもちろんアンナとフランチェスカ。
それぞれレシピ本を出版していたりと地元では食のエキスパートの二人。この二人と出会ったことで、食文化の素晴らしさや大切さに目覚めたと言っても過言ではない、大切な友人です。
 いつでも真剣に、でもお茶目にお話をするフランチェスカ。お惣菜店を家族で経営しながら歴史深い郷土食を研究しています。マンマのレシピでも数回登場してくれました。
いつでも真剣に、でもお茶目にお話をするフランチェスカ。お惣菜店を家族で経営しながら歴史深い郷土食を研究しています。マンマのレシピでも数回登場してくれました。 多くのレシピを研究し、ごく最近までアグリを経営していたことからお料理の腕はお墨付き、海外にもファンの多いアンナさん。私とはハーブ好きの仲間でもあります
多くのレシピを研究し、ごく最近までアグリを経営していたことからお料理の腕はお墨付き、海外にもファンの多いアンナさん。私とはハーブ好きの仲間でもあります🌿。
そもそも、なぜ私たちのアソシエーションがMac caroniという名前なのかちょっとお話しましょう。
時代は第2次世界大戦後、イタリアも参戦した国の1つですが、戦後のイタリアは職が無く多くのイタリア人は仕事を求めて海外へ。海外へ行けどやはり血はイタリア人、食べるものと言えばパスタ、パスタ、そしてパスタ(笑)だったそうです。当時は時代柄あまり学がなかった田舎出身の労働者も多く、そんなパスタばかり食べ田舎者的な振る舞いをしていたイタリア人たちは、総合的なパスタの別名、マッカローニばかりを食べる人種として、ちょっとした中傷的な意味も含めて食べ物そのものの名前で呼ばれていたのです。
そんな時代に想いを馳せた時、確かにこのような時代はあったにせよ、田舎で生まれたミクロテリトリー的な食文化や無数のマンマのレシピは今のイタリア食のべースになっていることは紛れもない真実ですから、そんな貧しい時代のイタリアから仕事を求めて移民として移住し、図らずも食の風習を継承していった多くの人々に敬意を払うと同時に、埋もれつつある食に光を当てたい、文化としての食にふれ合う機会を作りたい、という気持ちからこのマッカローニという名前が生まれました。
さて、ワークショップに話を戻しましょう。
チーズがテーマの食材だったこの回、どんなお料理を作ったのかご紹介しましょう。

こちらは3種の前菜、3色の野菜(インゲン、根セロリ、ニンジン)のテリーヌ、カショッタ•デイ•ウルビーノというチーズのラデイッキョ巻き、鶏肉のサラダのゴルゴンゾーラソース。どれもさっぱりとしていながらチーズの濃厚な美味しさは存在感があり、思わずおかわりしてしまいます😆。
 これがカショッタ•デイ•ウルビーノというチーズです。かのミケランジェロのお気に入りのチーズとして注文したという1545年付けの文書が残っており、DOPも獲得した牛乳と羊乳半々で作られた歴史の深いチーズです。
これがカショッタ•デイ•ウルビーノというチーズです。かのミケランジェロのお気に入りのチーズとして注文したという1545年付けの文書が残っており、DOPも獲得した牛乳と羊乳半々で作られた歴史の深いチーズです。 こちらはカプリーノというヤギのお乳のチーズを使った爽やかな1品。紫ビートの汁で作ったジュレを乗せて色鮮やかに。
こちらはカプリーノというヤギのお乳のチーズを使った爽やかな1品。紫ビートの汁で作ったジュレを乗せて色鮮やかに。 そしてこの不思議なパスタはこの日のメニューの主役です!
そしてこの不思議なパスタはこの日のメニューの主役です!パスタ•アル•サッコと呼ばれるこの1品。
その名の通り、イタリア語では”袋のパスタ”。
そう、このパスタ、チーズと小麦粉、卵を混ぜた生地を布袋に入れて、直接スープの中で煮るというとても珍しいパスタなんです。
 生地をよーく混ぜて…
生地をよーく混ぜて… 清潔な木綿の袋に入れます。
清潔な木綿の袋に入れます。 しっかりと紐で袋を結び、
しっかりと紐で袋を結び、 鶏と野菜たっぷりのスープにポン!笑。
鶏と野菜たっぷりのスープにポン!笑。 あとは1時間ほど煮込みます。
あとは1時間ほど煮込みます。このパスタは今ではすっかり作る人が減ってしまったいわゆる幻のパスタ。
今60代以上の方は小さい頃に良く食べたわー、とお話ししてくれましたが、私も見たのは今日がはじめて。
少しの生地でもスープをタップリ吸って膨らむので、家族の多かった農家などでは重宝されていたレシピだったそうです。これも僅かな食材でいかに家族全員のお腹を一杯にするかの工夫から生まれたものなのよ、とおしゃべりも弾みます🎵
 さて煮終わったパスタは袋から出されます。
さて煮終わったパスタは袋から出されます。固まりになってゴロリ。
 これをこうしてキューブ状に切って煮るのに使ったスープに戻します。
これをこうしてキューブ状に切って煮るのに使ったスープに戻します。 こんな風に素敵な1品に💕
こんな風に素敵な1品に💕南マルケのマチェラータでは、このパスタを3色に分けて作るそうで、スープに綺麗に映えるとか。それは是非やってみたい!と叫ぶ私•笑。
 一気にたくさん作ったので、皆さんちょっと一息。
一気にたくさん作ったので、皆さんちょっと一息。暖炉の炎の暖かさがゆるりとした空気を作り出してくれます。
 デザートはプリンの原型と言われているラッタローロというお菓子。みんなフランチェスカの話を真剣に聞いています。
デザートはプリンの原型と言われているラッタローロというお菓子。みんなフランチェスカの話を真剣に聞いています。こちらはチーズは入っていませんが昔からの農家の贅沢おやつとして紹介。レシピの歴史が大好きなフランチェスカ、彼女の昔のお話と絡めながら作っているとポピュラーなプリンも奥深いお菓子だと言うことに気着くのです。
 型から無事に出てきてくれました。
型から無事に出てきてくれました。 スープを取った鶏肉もまだまだ旨味が残っています。
スープを取った鶏肉もまだまだ旨味が残っています。細かく裂いて、オレンジとゴルゴンゾーラソースのサラダに。スミレの甘い香りが一杯の大変美味なサラダでした。
 こんな風に和気あいあいと終わったワークショップ。
こんな風に和気あいあいと終わったワークショップ。このアソシエーションが発足したのをきっかけに、これからも仲間たちと文化、食、歴史と芸術も絡めつつ面白い企画をたくさん紹介していければと思います。
共に過ごす、共に食することも料理を完成するエッセンスとして大切にする、Conviviale という素晴らしい言葉。この言葉をキーワードとしてまた色々なイベントを紹介していきますね。
それでは、また!😊

 皆さんこんにちは!
皆さんこんにちは! 我が家から数分車を走らせれば、すぐにこんなマルケらしい丘の連なりに出会えます。
我が家から数分車を走らせれば、すぐにこんなマルケらしい丘の連なりに出会えます。 野を歩くと、普段は雑草と思い込んでいるものでも知識さえあれば、食べられるものが沢山あるんです。
野を歩くと、普段は雑草と思い込んでいるものでも知識さえあれば、食べられるものが沢山あるんです。 この日収穫したのは主にこの3種類。
この日収穫したのは主にこの3種類。 へえ~、イタリア料理と野草??
へえ~、イタリア料理と野草?? さて、この日収穫した野草はよく洗い蒸したあと、ニンニクと。オリーブオイルでソテーに。
さて、この日収穫した野草はよく洗い蒸したあと、ニンニクと。オリーブオイルでソテーに。 まずは下の部分に切り込みを入れて均等に火が通るようにします。
まずは下の部分に切り込みを入れて均等に火が通るようにします。 春先の柔らかい野草であれば蒸すことをお勧めします。
春先の柔らかい野草であれば蒸すことをお勧めします。 蒸し上がった野草を刻んだニンニク、オリーブオイルと一緒にソテーに。
蒸し上がった野草を刻んだニンニク、オリーブオイルと一緒にソテーに。 ぐるぐるに巻いた生地を休ませて、丸く伸ばし、鉄板で色よく焼いて….
ぐるぐるに巻いた生地を休ませて、丸く伸ばし、鉄板で色よく焼いて…. そしてこちらもマイ豚さんの美味しいサルシッチャをじゅ~っと焼いて💓🐷
そしてこちらもマイ豚さんの美味しいサルシッチャをじゅ~っと焼いて💓🐷 熱々のうちに、クロストロに野草のソテーと一緒に挟んでかぶりつきます!!
熱々のうちに、クロストロに野草のソテーと一緒に挟んでかぶりつきます!! これはマルケ北部を旅する時には絶対に食さなければいけない1品。私のソウルフードと言っても過言ではありません🎵
これはマルケ北部を旅する時には絶対に食さなければいけない1品。私のソウルフードと言っても過言ではありません🎵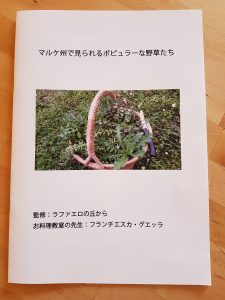 ボリジやダンデライオンなど、日本でもお馴染みのものから、あまり知られていないシラタマソウなどなど💓編集していても楽しかったです。
ボリジやダンデライオンなど、日本でもお馴染みのものから、あまり知られていないシラタマソウなどなど💓編集していても楽しかったです。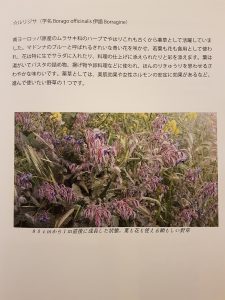 誰かマルケで一緒に野草摘みをして、お料理しませんか??😉🌿☘🍀
誰かマルケで一緒に野草摘みをして、お料理しませんか??😉🌿☘🍀 皆さんこんにちは!
皆さんこんにちは! 昔は家庭でも大切に育てた豚を自宅の仕事場で解体して、毛は筆に、血は料理やお菓子に使い、肉は全て無駄なく加工していたのは当たり前の習慣だったそう。
昔は家庭でも大切に育てた豚を自宅の仕事場で解体して、毛は筆に、血は料理やお菓子に使い、肉は全て無駄なく加工していたのは当たり前の習慣だったそう。 今回訪問したのは、ご近所で親戚も昔からの付き合いのあるアンジェロさんの小さな家族経営の工房。奥さんのガブリエラさんと2人で切り盛りしています。
今回訪問したのは、ご近所で親戚も昔からの付き合いのあるアンジェロさんの小さな家族経営の工房。奥さんのガブリエラさんと2人で切り盛りしています。 こじんまりとした工房内は質素で飾り気は全くありませんが、長年培ってきたサラミ熟成のための要素、田舎の美味しい空気、部屋の温度や湿度、熟成を促す良い菌がぎゅっとここに詰まっているのだな、と感じられる空間です。
こじんまりとした工房内は質素で飾り気は全くありませんが、長年培ってきたサラミ熟成のための要素、田舎の美味しい空気、部屋の温度や湿度、熟成を促す良い菌がぎゅっとここに詰まっているのだな、と感じられる空間です。 二人の工房があるのはトリュフで有名なアクアラーニャの丘の上。冬は寒さが厳しいですが、キーンと気持ちのよいきれいな空気。
二人の工房があるのはトリュフで有名なアクアラーニャの丘の上。冬は寒さが厳しいですが、キーンと気持ちのよいきれいな空気。 工房内には熟成の終わったサラミたちがぶら下がり、熟成の香りが漂っています。
工房内には熟成の終わったサラミたちがぶら下がり、熟成の香りが漂っています。 奥さんが休憩しつつ暖炉の薪で焼いてくれる新鮮なお肉が美味しすぎる!!シンプルにパンと一緒に。
奥さんが休憩しつつ暖炉の薪で焼いてくれる新鮮なお肉が美味しすぎる!!シンプルにパンと一緒に。 腿のプロシュットになる部分の掃除はやっぱり見応えあり!立派な腿の持ち主は200キロくらいだったそうです。
腿のプロシュットになる部分の掃除はやっぱり見応えあり!立派な腿の持ち主は200キロくらいだったそうです。 私はサルシッチャ作りのお手伝い😆。
私はサルシッチャ作りのお手伝い😆。 腸に味を着けて挽いた肉を詰めていく作業はこの機械で。もちろん保存料も着色料も一切使いません。
腸に味を着けて挽いた肉を詰めていく作業はこの機械で。もちろん保存料も着色料も一切使いません。
 サラミもきれいに出来ました!
サラミもきれいに出来ました! 豚を解体すると副産物として出来る沢山の上質なラード。これは揚げ物に持ってこいなんです。高温にしても質が変わりにくい豚のラード。思ったよりさらっとカラッと揚がるんですよ!
豚を解体すると副産物として出来る沢山の上質なラード。これは揚げ物に持ってこいなんです。高温にしても質が変わりにくい豚のラード。思ったよりさらっとカラッと揚がるんですよ! 季節は奇しくもカルネバーレ。この季節に何故揚げ菓子が多いのか、豚仕事の歴史と絡めて考えればなるほど頷けます。我が家もマルケのカルネバーレの揚げ菓子、チチェルキアータを早速作りました!
季節は奇しくもカルネバーレ。この季節に何故揚げ菓子が多いのか、豚仕事の歴史と絡めて考えればなるほど頷けます。我が家もマルケのカルネバーレの揚げ菓子、チチェルキアータを早速作りました! スローフードに登録されている特産品、チチェルキアというお豆の形にちなんでいると言うこのお菓子、我が家も全員大好物です。
スローフードに登録されている特産品、チチェルキアというお豆の形にちなんでいると言うこのお菓子、我が家も全員大好物です。