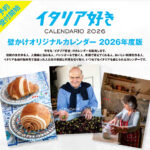とっても古い教会で、10世紀に建てられました。(その後改築され現在の姿に)
Vigneとは葡萄畑のことで、昔は、この辺りに葡萄畑があったそうです。
今は建物(それでも14、15世紀ごろからある)が立ち並んでそんな面影は一切ありませんが…!
この教会に入って右手すぐにある一角に、子宝スポットがあるのです。
一本の柱の周りに大量のよだれかけ!

左側は男の子の名前、右側は女の子の名前が刺繍されたよだれかけが飾られています。

これは恐らく古代ローマ人が作った古い柱と伝えられていて、この教会を建てる時(10世紀)に使用されたもの。
その後14〜15世紀にマリア様がイエスに授乳する様子が描かれました。
18世紀に後期バロック風の金色の装飾のケースで囲われる今の姿になりました。(この教会がバロック風の装飾なのでそれに合わせて)
それにしても数え切れないほどのよだれかけ…ご利益があるのでしょうね。
日本でも子宝神社や安産祈願などがありますので、イタリア人もこんな風に神さまにお祈りするんだなぁと接点を感じました^ ^
皆さんに幸あれ〜ということで私もお賽銭を入れてロウソクを立てました。
すると若い女性がお祈りに来ました。2人目を授かりたいみたいでしたよ!
本人だけでなく、友人や家族も祈祷に来るみたいです。
ちなみに、この左隣の祭壇、一見普通の祭壇ですが少し変わっています。

「郵便配達人たちの協会の祭壇」(現在の郵便、電信、電話局員)とプラカードに書いてありました。
教会内の小さな祭壇は、ほとんどが「○○家」と貴族の名字が連なっているのですが、こちらは通信関連の仕事の団体の寄付金によって作られたもののようです。珍しい!
さてさて、先日までジェノヴァで毎年開催されるヨット、ボートの大きな展示会がありました。毎年街の中が少し盛り上がるのですが、今年はGENOVAという名前の香水が街中に置かれました!

この展示会のために作られた香りだそうです。
さてその香りとは……!
バジルがベースになった、うーん……悪くはないけど、どうなんだろうか…まあ、感想に難しい微妙な香りでした。(私の個人の意見です笑)
バジルが結構前に出ているので、どうしてもジェノヴェーゼソースのことを思い出してしまい、香りに酔うというより、お腹が空くという香り…かな。笑
中心地の至る所(時に個人経営のお店の前など)に展示されていますので、ぜひ興味のある方は是非ジェノヴァをイメージして作られた香水を嗅いでみてくださいね!









 焼けたら熱々のまま直ぐにテーブルへ!
焼けたら熱々のまま直ぐにテーブルへ!









 今年は5月の長雨にせっかく咲いた花の蜜が流れてしまい、蜂蜜が採れないどころか、ミツバチの食料となるミツも不足で沢山の群れが死んでしまったり、分峰していなくなってしまったりという被害がエミリアロマーニャ州を始めイタリア全国で報告されていました。
今年は5月の長雨にせっかく咲いた花の蜜が流れてしまい、蜂蜜が採れないどころか、ミツバチの食料となるミツも不足で沢山の群れが死んでしまったり、分峰していなくなってしまったりという被害がエミリアロマーニャ州を始めイタリア全国で報告されていました。 その反面たまたま、急な雨が降った時に写真の分蜂の群れを見つけて、うちの子に加わった群もいるのです。
その反面たまたま、急な雨が降った時に写真の分蜂の群れを見つけて、うちの子に加わった群もいるのです。 ミツバチは貯蔵した巣穴が蜜が一杯になると蜜蝋で蓋をします。これをナイフで削り取り、ドラム缶に均等になるように差し込み、手回しの遠心分離機にかけてハチミツを取り出します。
ミツバチは貯蔵した巣穴が蜜が一杯になると蜜蝋で蓋をします。これをナイフで削り取り、ドラム缶に均等になるように差し込み、手回しの遠心分離機にかけてハチミツを取り出します。 黄金色のハチミツが流れ出てくる様子は圧巻!でもこれだけでは、ハチミツに混じった蜜蝋などが混じって、食感が悪いので、最低10日間寝かせます。すると蜜蝋が上にたまり、ハチミツと分かれるので、綺麗なハチミツが採取できるのです。
黄金色のハチミツが流れ出てくる様子は圧巻!でもこれだけでは、ハチミツに混じった蜜蝋などが混じって、食感が悪いので、最低10日間寝かせます。すると蜜蝋が上にたまり、ハチミツと分かれるので、綺麗なハチミツが採取できるのです。 3月の上旬から咲く、果樹の花桃、プラム、桜、を始め、アカシア、シナノキ、我が家の周りはパルミジャーノの牧草を栽培しているので、エルバメディカと呼ばれる牧草のお花などなどイタリア語でMiele di mille fiori 千の花の蜜。(和名ならば百花蜜)味も香りも濃厚。同じ牧草を食べて育った牛の乳から作るパルミジャーノレッジャーノチーズとの相性も抜群です。
3月の上旬から咲く、果樹の花桃、プラム、桜、を始め、アカシア、シナノキ、我が家の周りはパルミジャーノの牧草を栽培しているので、エルバメディカと呼ばれる牧草のお花などなどイタリア語でMiele di mille fiori 千の花の蜜。(和名ならば百花蜜)味も香りも濃厚。同じ牧草を食べて育った牛の乳から作るパルミジャーノレッジャーノチーズとの相性も抜群です。 その土地でできたものはその土地のものとよくあう!
その土地でできたものはその土地のものとよくあう! バルサミコ酢醸造室の見学、試飲講習会、郷土料理のお食事会、料理教室のお問い合わせは
バルサミコ酢醸造室の見学、試飲講習会、郷土料理のお食事会、料理教室のお問い合わせは


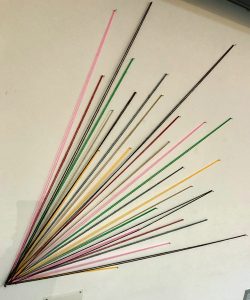





 日暮れ時は特に綺麗。
日暮れ時は特に綺麗。 サレルノ以南は高速料金無料!
サレルノ以南は高速料金無料! ガラスが汚いのはご愛敬です・・
ガラスが汚いのはご愛敬です・・ 一般道の港までの道筋で、少しわかり難いのがレッジョカラブリア駅周辺。
一般道の港までの道筋で、少しわかり難いのがレッジョカラブリア駅周辺。 メッシーナ行きのゲートをくぐれば、いよいよフェリー乗り場。乗船直前に係員がチケットのバーコードを読み取って確認します。それでは、乗船~
メッシーナ行きのゲートをくぐれば、いよいよフェリー乗り場。乗船直前に係員がチケットのバーコードを読み取って確認します。それでは、乗船~ メッシーナ海峡を航行するカーフェリーには何種類かあって、漁船(?)な小さ目な船から、船体内部が3階建てぐらいの駐車場になっている大型船までさまざま。
メッシーナ海峡を航行するカーフェリーには何種類かあって、漁船(?)な小さ目な船から、船体内部が3階建てぐらいの駐車場になっている大型船までさまざま。 運が良いと大型船に当たる事もあります♪ 今回の旅では帰路が大型船でした。子供用の遊戯施設など+αな設備を備え、駐車場もなんだかカッコいいんですよね。
運が良いと大型船に当たる事もあります♪ 今回の旅では帰路が大型船でした。子供用の遊戯施設など+αな設備を備え、駐車場もなんだかカッコいいんですよね。 ちなみに、船内は犬や猫も歩かせてOKです。ただし、リードの着用と口輪の装着を求められます。
ちなみに、船内は犬や猫も歩かせてOKです。ただし、リードの着用と口輪の装着を求められます。 口輪!とびっくりしますが、実際のところは口輪は持っていればOKで、余程のことが無い限りは装着を求められません。
口輪!とびっくりしますが、実際のところは口輪は持っていればOKで、余程のことが無い限りは装着を求められません。 約30分の海峡越え。船内のバーでアランチーニを食べたり、
約30分の海峡越え。船内のバーでアランチーニを食べたり、 往来するフェリーや遠くの漁船を眺めながらゆったりと過ごしているともうシチリア! どうぞ良い旅を!
往来するフェリーや遠くの漁船を眺めながらゆったりと過ごしているともうシチリア! どうぞ良い旅を!











 同地区内、緑豊かな高原が連なる広大な地域。軽いハイキングから、リフュージョと言われる山小屋やマルガと呼ばれる牛の放牧場とチーズ製造所等があり、食事などを楽しむ場所であるため、バカンスシーズンはどこも人でいっぱいだ。
同地区内、緑豊かな高原が連なる広大な地域。軽いハイキングから、リフュージョと言われる山小屋やマルガと呼ばれる牛の放牧場とチーズ製造所等があり、食事などを楽しむ場所であるため、バカンスシーズンはどこも人でいっぱいだ。 売り場脇にある製造現場を覗かせてもらった。
売り場脇にある製造現場を覗かせてもらった。
 今やほぼ他では皆無に等しい、薪で炊くカルダイア(乳を温める鍋)。ガスなんか使うよりもこの周辺にある木々を使って、経済的にもまたエコ的にも優れているから当然!とご主人は話す。長年の経験での火加減の調節だから、ガスよりも、実際に燃え具合を目で見ながら火力調節、温度調節ができる自然の炎のほうが、彼にとっては簡単なのだそうだ。
今やほぼ他では皆無に等しい、薪で炊くカルダイア(乳を温める鍋)。ガスなんか使うよりもこの周辺にある木々を使って、経済的にもまたエコ的にも優れているから当然!とご主人は話す。長年の経験での火加減の調節だから、ガスよりも、実際に燃え具合を目で見ながら火力調節、温度調節ができる自然の炎のほうが、彼にとっては簡単なのだそうだ。 そして、チーズの熟成室。D.O.P.の認証を得るには、もはや衛生的には検査に通らない木枠。なんともいい味わい。だから、もちろんここのチーズはD.O.P.の認証はない。
そして、チーズの熟成室。D.O.P.の認証を得るには、もはや衛生的には検査に通らない木枠。なんともいい味わい。だから、もちろんここのチーズはD.O.P.の認証はない。 熟成室の外にはここでできるリコッタを燻製する燻製機が。ちょっと傾いた感じでいるところがこれも味わいのある風景。この時も燻製作業中だ。
熟成室の外にはここでできるリコッタを燻製する燻製機が。ちょっと傾いた感じでいるところがこれも味わいのある風景。この時も燻製作業中だ。 ここでチーズが作られるのは、牛の放牧期間である5月から9月いっぱいくらいまで。そのため、フレッシュ、及び熟成期間の短いチーズの販売はこの期間のみ。その後は熟成タイプのもののみが彼らの手元に残る。
ここでチーズが作られるのは、牛の放牧期間である5月から9月いっぱいくらいまで。そのため、フレッシュ、及び熟成期間の短いチーズの販売はこの期間のみ。その後は熟成タイプのもののみが彼らの手元に残る。 チーズの美味しさはその原料となる乳に由来するものだから、こんな大自然のなかでのびのびと過ごしている乳牛からとれる乳は美味しく、風味の豊かさが格段によい。見た目も黄色味が非常に強いものとなる。
チーズの美味しさはその原料となる乳に由来するものだから、こんな大自然のなかでのびのびと過ごしている乳牛からとれる乳は美味しく、風味の豊かさが格段によい。見た目も黄色味が非常に強いものとなる。