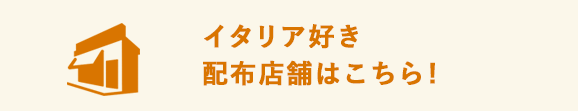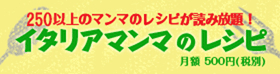轟々と燃え上がる炎、もくもくと立ち上る黒煙。ちっちゃくて重たい口をぱかっと開いたのが、まるで穴蔵に巨大な胴体を押し込んで冬眠している怪獣のあくびみたい。
 マンマのレシピに登場してもらったフラヴィアさんの住むドゥエ村の共同釜はまるで生き物のようでした。
マンマのレシピに登場してもらったフラヴィアさんの住むドゥエ村の共同釜はまるで生き物のようでした。この釜が目覚めるのは一年にたった一度、11月最後の土日で一昼夜のみ。年一回だからパン作りに関わる仲間たちの手も鈍りそうなものなのに、とにかくこの村の人たちは手際がよいのです。
 『イタリア好き』のために自宅で伝統料理のレシピを披露してくれたアオスタのマンマのフラヴィアさんは、取材のあと、貴方たちは運が良いわねと正にそのパン作りの現場に連れて行ってくれたのです。寒さをこらえて釜の前で半時間ほど待機していると、やって来ました『パン焼きたい(隊)』!
『イタリア好き』のために自宅で伝統料理のレシピを披露してくれたアオスタのマンマのフラヴィアさんは、取材のあと、貴方たちは運が良いわねと正にそのパン作りの現場に連れて行ってくれたのです。寒さをこらえて釜の前で半時間ほど待機していると、やって来ました『パン焼きたい(隊)』! 作業全体を仕切るのは農業担当の議員も務めるディーノ、パンの焼き具合をみるグループ最年長のマリオ。実際に焼成を担当するのはジョルジョは酪農を営んでいるそう。それぞれの役割分担がばっちり決まっている。
作業全体を仕切るのは農業担当の議員も務めるディーノ、パンの焼き具合をみるグループ最年長のマリオ。実際に焼成を担当するのはジョルジョは酪農を営んでいるそう。それぞれの役割分担がばっちり決まっている。
寒いからかみんな口数は少ないけど、なんだか一様に目が笑ってる。運搬係の少年も笑っている。
 まずは、エスプレッソをご近所のキッチンで入れたのを若手がもってくれるとそれをすすり、一呼吸おいたらさあ作業開始!
まずは、エスプレッソをご近所のキッチンで入れたのを若手がもってくれるとそれをすすり、一呼吸おいたらさあ作業開始!先に焼いてあったものは荒熱がとれていて少年が籐籠で運搬用のトラックに運び、
 ディーノが少年と配布所に運んでいった。ジョルジョが釜の扉を空けて外付けのライトで釜の中を照らし、パン表面の焼き目から焼き上がったと思われるものを順に引き出してきます。
ディーノが少年と配布所に運んでいった。ジョルジョが釜の扉を空けて外付けのライトで釜の中を照らし、パン表面の焼き目から焼き上がったと思われるものを順に引き出してきます。 ジョルジョが引き出すとマリオが厚手の軍手をした手で受けてパンの裏をコンコン叩く。
ジョルジョが引き出すとマリオが厚手の軍手をした手で受けてパンの裏をコンコン叩く。「マリオは叩いた音だけで焼き具合がはっきり判るのよ。」
フラヴィアさんは胸を張って言い切ります。マンマのレシピ紹介のための取材中も最後まで話すのをためらっていましたが、実は村の文化・社会福祉担当の議員をしていて、この「パン焼きデー」でも総責任者としてすべてを仕切っていたのも彼女でした。
 マリオがパンの背中をコンコンとノックして、焼けていたら棚に並べて荒熱をとれるのを待ちます。焼けていなかったら釜に戻し、ジョルジョが釜の熱のより高い奥に放り投げ、手前のパンを引っ張り出す。作業の間、あまーいパンの香りが釜のある屋内とも屋外ともつかない不思議な空間いっぱいに広がりました。
マリオがパンの背中をコンコンとノックして、焼けていたら棚に並べて荒熱をとれるのを待ちます。焼けていなかったら釜に戻し、ジョルジョが釜の熱のより高い奥に放り投げ、手前のパンを引っ張り出す。作業の間、あまーいパンの香りが釜のある屋内とも屋外ともつかない不思議な空間いっぱいに広がりました。焼かれるパンは2種類。
 カラス麦の全粒粉100%の黒パン(Pane Nero)と、小麦の全粒粉に干しブドウを加えて焼く甘いパン(Dolce)。
カラス麦の全粒粉100%の黒パン(Pane Nero)と、小麦の全粒粉に干しブドウを加えて焼く甘いパン(Dolce)。 これを村のみんなで捏ねて、みんなで発酵させ、徹夜で焼き続ける。 一回に焼けるのは120個。とにかく村の住人にすべていきわたるまで15回程度焼き続ける。
これを村のみんなで捏ねて、みんなで発酵させ、徹夜で焼き続ける。 一回に焼けるのは120個。とにかく村の住人にすべていきわたるまで15回程度焼き続ける。「このパンはね、昔は一回焼いたらそれを1年間食べ続けてたのよ。」とフラヴィア。 「ヘッ!? 1年後ってこのパンはどうなっているの?」
「歯の間でクリッ、クリッ、クリッてなるの」その音を思い浮かべて口元をクリッとさせ、嬉しそうな眼差しのフラヴィア。
 最後のパンを釜から出し終えると、火おこし担当のジョルジョが再び釜の上部にある鉄製の排気口を三つとも全開にし、釜の中に薪を井桁に組んで点火、あれこれ手を動かして炎が音を立てだす頃には、夕闇がそこまで迫っていました。
最後のパンを釜から出し終えると、火おこし担当のジョルジョが再び釜の上部にある鉄製の排気口を三つとも全開にし、釜の中に薪を井桁に組んで点火、あれこれ手を動かして炎が音を立てだす頃には、夕闇がそこまで迫っていました。 台所のオーブンでも、お鍋でも、木べら一本だって値段やデザインとは関係なく使い込んでいくうちに独特の表情のでる道具というのがあるものです。ドゥエ村のこの共同釜は上部が給水層、下層部がこの焼き釜という不思議な構造で1900年頃に作られたとされていますが、小さいながら手入れがとても行き届いていました。
台所のオーブンでも、お鍋でも、木べら一本だって値段やデザインとは関係なく使い込んでいくうちに独特の表情のでる道具というのがあるものです。ドゥエ村のこの共同釜は上部が給水層、下層部がこの焼き釜という不思議な構造で1900年頃に作られたとされていますが、小さいながら手入れがとても行き届いていました。
誰のものというのではない公共の施設は、運営予算が不足するとたちまち放置されがちですが、この小さな村の500人の住人は自分の生活基盤を構成する施設を絆といっしょに前向きに共有しているという意識があって、予算云々の前に目の前にあるものを大事に使っているから、私の目にはこの釜が生き物のように……そう思えてきました。

フラヴィアが無理をして分けてくれたドゥエ村のパンを自宅に戻って口にしてはっとしました。黒パンの皮の一番固いところが「クリッ」。それを噛み砕いていったら、これまで味わったことのない香ばしさと麦が持つ色んな味わいが次々に浮かんでは消えていきました。
 今年の11月には生地捏ねから発酵、焼成まで全工程に携わる村の人たちに会いにいくつもりです。
今年の11月には生地捏ねから発酵、焼成まで全工程に携わる村の人たちに会いにいくつもりです。