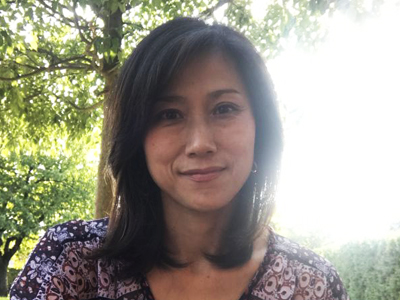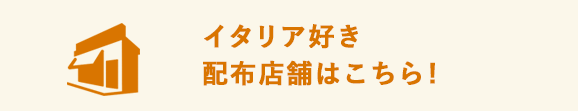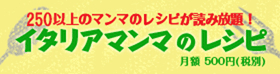クチーナ•ポーヴェラ再考@マルケ
 皆さんこんにちは!
皆さんこんにちは!マルケ州は初夏となりつつある今日この頃です。
この春はつい先日出た、イタリア好きマルケ特集号のコーデイネートをさせていただく機会に恵まれ、大切な友人達を紹介することが出来てとても記念になるお仕事となりました。
そして今回の仕事を振り返りつつ再考していたある1つのこと。
それは、クチーナ•ポーヴェラ。
 野生のアザミを使ったリゾット、農家の食事には野草がたくさん取り入れられていた
野生のアザミを使ったリゾット、農家の食事には野草がたくさん取り入れられていたクチーナはお馴染みの言葉で料理や台所を意味し、ポーヴェラとは”貧しい”という意味合いの言葉ですが、ここでは決して”貧民や貧乏人”という意味合いではなく、”手元や身の回りにある限られた食材(=貧しいという意味合い)”をうまく利用して作られた料理をさしています。
(貧民の料理だと、クチーナ•デイ•ポーヴェリが正しい表現になります🎶)
特に冬の収穫物は底を尽きつつあり、春、夏の収穫にはまだまだ時間のかかる早春などは野で取れる野草などが頻繁に使われていましたし、今ではスローフードのプレシデイオになっているチチエルキアのように家畜用に栽培されていた豆類なども昔は人間にも食べられていました。
1970年代に生まれたと言うこの言葉。それ以前は農家の家庭での当たり前の事実だったので敢えてボキャブラリーは存在していませんでしたが、高度経済成長期にイタリア人の食は大きく変化し、農家のレシピや食材が忘れ去られつつあったこの時代、古いものを食べ続けることに、都会に出た若者たちは嫌悪感さえ感じていたといいます。
そんな時代に逆流しながら戦ってきた人たちが、このマルケ特集号ではちょこちょこと取り上げられています
 精製ラードの副産物、チッチョリを仕込むカルロ
精製ラードの副産物、チッチョリを仕込むカルロイタリアでは、1964年から1982年という18年もの時間をかけて廃止になったメッザドリアという小作人制度がありましたが、メッザ(半分)という言葉からも分かる通り地主に収穫の半分を納めるというものでした。
他の中部イタリアの州と同じくマルケの農地の大部分もこのメッザドリアによって耕作されていたのですが、大家族だったこの時代、一家全員の食料を確保して限られた食材で家庭の台所を切り盛りするのは女性の役目でした。
家の家畜を解体しても、精肉は地主や神父さんへ行き、自分達は主に残った内臓を工夫して調理する。
パンやパスタの小麦はとても貴重なので、かさ増し出来るよう、栗の粉やソラマメの粉を練り混んで生地を作る…
 レバーを網脂とローリエで包んで作るフェガテイーニ
レバーを網脂とローリエで包んで作るフェガテイーニそんなマンマたちの工夫や努力を見て育って来たのが現在生産者として活躍中のジェネレーション。
まだまだ男尊女卑だった時代の、ある意味無学のステレオタイプなコンタデイーニ(農耕人)から脱出し、大学を卒業し、自らの選択として、新しい形のファームの在り方を模索する生産者が文字通り挑戦し、戦っています。
 お連れしたお客様とトークが炸裂する、ファームの女将さんジージャ
お連れしたお客様とトークが炸裂する、ファームの女将さんジージャ「昔はね、豚の解体っていっても、小さな農家一件一件に工房は無かったから、村で大きな工房を持っている農家に自分の豚を持って行って、工房を借りて村人たちに手伝ってもらいながら今日は誰々の手伝い、明日は誰々の手伝い..というふうに協力しあって成り立っていたの。今のヨーロッパ共同体が作った規定は、どんなに小さくても生産者は自分のところにをきちんと作業場を作らなければいけない、という理不尽なもので、一件一件ものすごく費用がかかるし、集って協力しあう、ということがなくなってしまったわ。
豚は捨てる所が無いって昔から言われていて、以前は抜いた血ですらお菓子やおかずに使われていたの。でも今の規定では血すら使ってはいけないと言われる。
まるで先人が体に悪いものを食べてきたかのように。
クチーナ•ポーヴェラという言葉だけが一人歩きして、耳障りのいい言葉として薄っぺらなライフスタイルの提案をしている本なんかを読むとちょっと憤慨するわ。本質について問う人は本当に減ってしまったのは残念よ。
私も昔にしがみつきたいんじゃないの。自分だって閉鎖的な昔ながらの農家から飛び出してきた人間だしね。
でも誰かが伝承しなきゃいけないし、体現しなきゃ伝わらないでしょ?
どこまで続けられるか分からないけれど、自分にとっての理想的なファームの在り方-家畜の藁や牧草の栽培から始まり、放し飼いの野生に近い状態で育った家畜から昔ながらの製法のハムやサラミの保存食を作る、出来るだけ自給自足の形でね。」
この話しをしてくれたのは、夫婦で経営しているファームの奥さん、ジージャ。
ハム•サラミ製造の生産者としては業界でそれなりに知られ、海外でのワークショップやスローフード協会の祭典、サローネでもワークショップなどをやって来た。アメリカに初めて輸入されたチンタ•セネーゼの種豚は彼らの飼育したものだ。
でも価値観の違いやビジネスの影の部分に違和感を覚えて遠ざかり、自分達に正直にやっていこうと決めたそう。

ウルビーノ近郊の丘に暮らし、どこの店にも卸していないにのにも関わらず、彼らの作るサラミやハムやパンを求めて足を運ぶ人はあとを絶ちません。
今回の取材のお仕事でも再確認した、”クチーナ•ポーヴェラの本質”ということ。
こういった方たちの体現する食文化が、どうぞこれからも残っていきますように、と強く願った春でした。
皆さんも是非、このマルケ特集号を手にとってみられて下さいね!
それでは、また!